太陽光発電事業の業界動向、M&A・売却・買収事例30選

太陽光発電事業は近年M&Aが活発な業界の一つです。太陽光発電事業は再生可能エネルギーに関わる制度・法改正の影響を受けやすい業界です。
本記事では、そうした太陽光発電の市場動向を解説するとともに、太陽光発電事業におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。
太陽光発電の概要・市場動向
太陽光発電とは
太陽光発電事業とは、家屋の屋根などに取り付けた太陽電池を用いて太陽光を電気に変換する、太陽光発電に関連した事業を展開する事業をいいます。
太陽光発電設備は、10kw未満は住居用に、10kw以上は産業用に分類されるほか、1,000kw以上のシステムはメガソーラーと呼ばれます。
太陽光発電事業者は余剰電力を電力会社などに売却する売電事業者、太陽光パネルの設置・施工を行う太陽光発電設備施工業者、太陽光発電の管理メンテナンスを担うO&M事業者に分類されます。
太陽光発電の市場動向
FIT法導入による市場拡大
太陽光発電市場はFIT法の影響を受けて変動しています。
FIT法とは、2012年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」によって定められた固定価格買取制度を指します。
かつては再生可能エネルギー(以後、再エネ)による発電はコストが高く導入が進まないという課題があったため、再エネ発電による電力を他の電力よりも高い価格で買い取ることで、再エネ導入を促進することを目的に制定されました。
FIT法の導入により太陽光発電設備の認定及び導入要領は急増し、それに伴い買取電力量も増加しました。
経済産業省資源エネルギー庁「買取電力量及び買取金額の推移」によると、同制度が導入された平成24年度から25年度にかけて固定価格買取制度における太陽光発電設備を用いた発電電力量の買取電力量は10kw未満が232,068万kWhから485,686万kWhに、10kW以上では18,953万kWhから425,467万kWhまで増加しています。特に、10kw以上の太陽光発電の買取電力量は令和3年に6,961,027万kWhまで達しており、一貫して増加傾向にあります。
FIT法改正による事業者の負担増加
FIT法の導入は太陽光発電業界に追い風となりましたが、2017年にFIT法が改正されたことで事業者への負担が増加しました。FIT法の導入後に明らかになった課題として、一般社団法人太陽光発電保安協会「改正FIT法とは?」では以下の3つの課題が挙げられています。
第一に、電気を買い取るための国民負担が増加したことです。電力会社が再エネ電力を買い取る際のコストの一部は、再エネ賦課金として電力価格に上乗せされており、2021年度の賦課金総額は2.7兆円に及んでいました。
第二に、日差しがない時間帯は発電できない設備の導入が増加したことです。
第三に、電気を売る権利を有していながら発電しない事例が増加したことです。FITによる買取価格は認定時の太陽光パネルの価格などを基に設定されているため、認定を受けるだけで発電を始めない事業者がいると、太陽光パネルの価格が低下しても賦課金による国民負担が減少しない問題が指摘されていました。
これらの課題を解決するためにFIT法が改正されたことで、事業者に事業計画書の提出が義務化されたほか、太陽光発電システムのメンテナンスも義務化されました。
結果として、設備投資を行う経済的余裕がない企業は新制度への対応が困難になり、メンテナンスを行ってこなかった中小企業には大きな負担となりました。現在では後述するFIP法がFIT法と併せて施行されているため、太陽光発電事業者は常に法制度を注視することが不可欠です。
FIP法の導入
FIT法と並行して2022年4月からFIP法も導入されました。
FIT法では買取価格が固定されている一方、FIP法では市場価格にプレミアムが上乗せされる形で買取価格が決定されるため、買取価格が市場価格と連動するという違いがあります。
FIT法は再エネの導入を促す目的で定められましたが、FIP法は他エネルギーのように再エネも需給バランスに応じて発電量を調節することで、カーボンニュートラルの実現に向けて再エネの自立を促すために導入されました。
また、再エネ賦課金の負担を減少させるためには電力を市場で取引できるようにしなければならないため、移行措置の一環としてFIP法が導入されたという背景もあります。
FIP法のメリットとしては、複数の発電事業者がグループとなり電力を販売したり、蓄電池を活用することで市場価格が高い時に電力を販売することで収益拡大が見込めることが挙げられます。一方で、計画通りに発電できなかった際のペナルティ料金などを指すバランシングコストの負担や、価格変動により利益の予測が難しいことがデメリットとなります。
買取価格の変動に着目した今後のビジネスとしてアグリゲーションビジネスが着目されています。これは発電事業者と電力市場の間に入り、電力の需給調整を代行するビジネスをいいます。
FIT法においては再エネ事業者が電力受給を管理をする必要はなかったですが、変動する価格に対応するためには電力販売のタイミングを適切に分散させることが必要になります。
こうした役割を担うアグリゲーターの必要性は資源エネルギー庁「FIP法の詳細設計とアグリゲーションビジネスの更なる活性化」にも明記されており、新たな制度に伴うビジネスチャンスとも捉えられます。
省エネ法改正による需要拡大
2023年4月施行の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称、省エネ法)」は、企業の太陽光発電導入を促進することが期待されています。
今回の改正では、エネルギー使用の合理化の対象として化石エネルギーに加えて非化石エネルギーも追加され、エネルギーの定義が見直されました。
また、需要サイドでも非化石エネルギーへの転換が求められるようになりました。これまでは非化石エネルギーへの転換は事業者の自主的な取り組みとされてきましたが、改正後は非化石エネルギーの使用割合向上、エネルギー転換に関する中長期的な計画作成などが求められるようになりました。
太陽光発電は非化石エネルギーの中でも導入は比較的容易であるため、省エネ法改正は太陽光発電業界にとって事業拡大の好機であると考えられます。
太陽光発電事業のM&A動向
太陽光発電業界では、相次ぐ制度・法改正に対応できなくなった企業を売り手としたM&Aが頻繁に見られます。
2017年のFIT法改正では、大規模な設備投資が求められる企業やメンテナンス事業を手掛けていない企業による譲渡ニーズが急速に高まりました。
一方、太陽光発電の需要自体は今後も成長することが期待されているため、早期に事業を開始して安定的な収益を確保している企業を買収するニーズも高まっています。
法・制度の改正は既存事業者の存続に大きな影響を与えることから、今後の改正次第でM&Aの必要性も変動することに注意する必要があります。
太陽光発電事業におけるM&Aのメリット
売り手のメリット
太陽光発電業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。
- 定期報告や情報開示を体系化できる
- 保守点検体制を強化することができる
- 買い手の資本力を梃子に設備投資を実行できる
- 株式譲渡による譲渡収入とともに事業から退くことができる
- M&Aを契機に代表者による借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
太陽光発電業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。
- 既に認定を受けた事業者を買収することで販売単価を高く設定できる
- 事業参入に際して認定取得などの初期手続きを省略できる
- 売り手の抱える有資格者を確保できる
- 発電所のポートフォリオを分散できる
- 再エネ事業に貢献することで社会的イメージの向上に繋がる
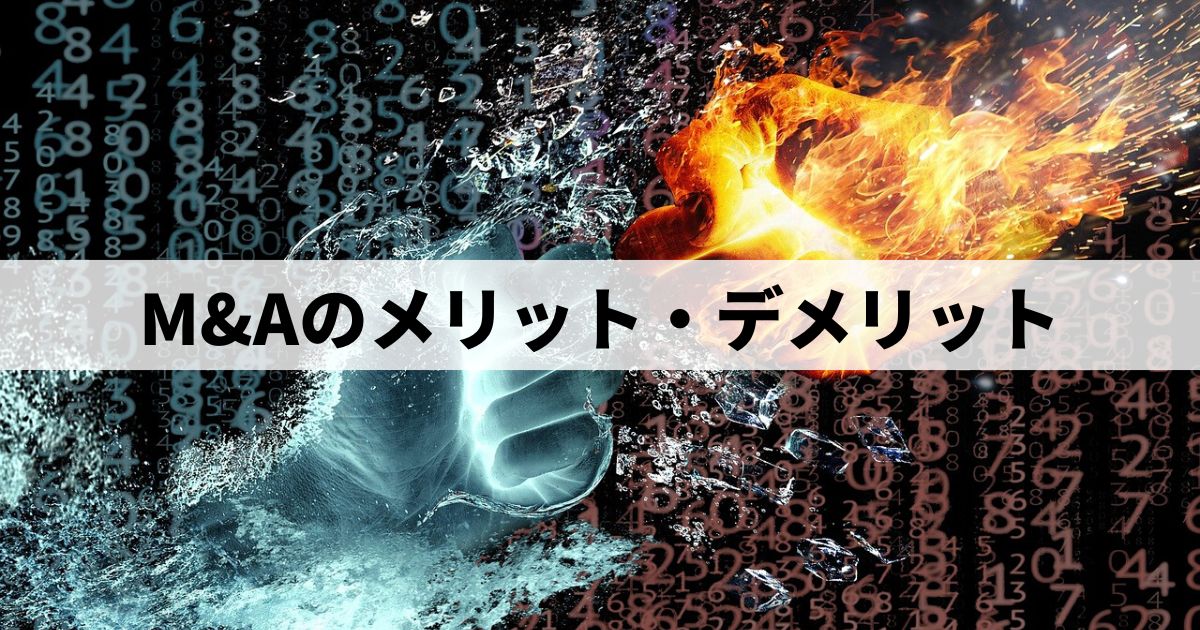
太陽光発電事業のM&A・売却・買収事例
フィットによるPlus one percentのM&A
クリーンエネルギー事業、スマートホーム事業、フランチャイズ事業を手掛けるフィットは、太陽光発電システム開発および販売を手掛けるPlus one percentの全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年11月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:四国及び西日本エリアでのシェア拡大
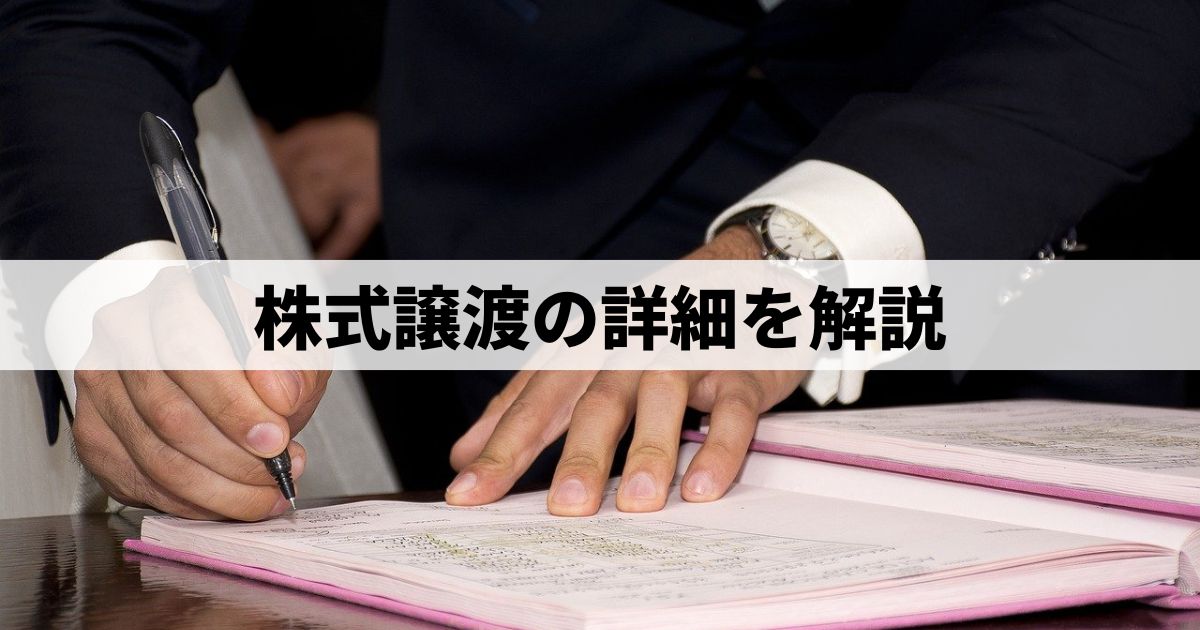
Abalanceによる産業用太陽光発電事業のM&A
グリーンエネルギー事業、建設機械事業、IT事業、ヘルスケア関連事業を手掛けるAbalanceは、グループ会社であるWWBを通じて、太陽光発電システムの販売・施工、太陽光発電事業及び電力の卸売事業を手掛ける日本ライフサポートから産業用太陽光発電事業を譲り受けました。
- 実行時期:2021年11月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:バリューチェーンの拡充

ENEOSホールディングスによるジャパン・リニューアブル・エナジーのM&A
石油製品(ガソリン・灯油・潤滑油等)の精製および販売、ガス・石炭の輸入および販売、石油化学製品等の製造および販売、電気・水素の供給を手掛けるENEOSホールディングスは、ゴールドマンサックス傘下で発電プラントに関する事前調査、計画、設計、関連資材調達及び販売などを手掛けるジャパン・リニューアブル・エナジーの全株式を取得しました。
- 実行時期:2022年1月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:2,000億円
- 目的:再生可能エネルギー事業の拡大
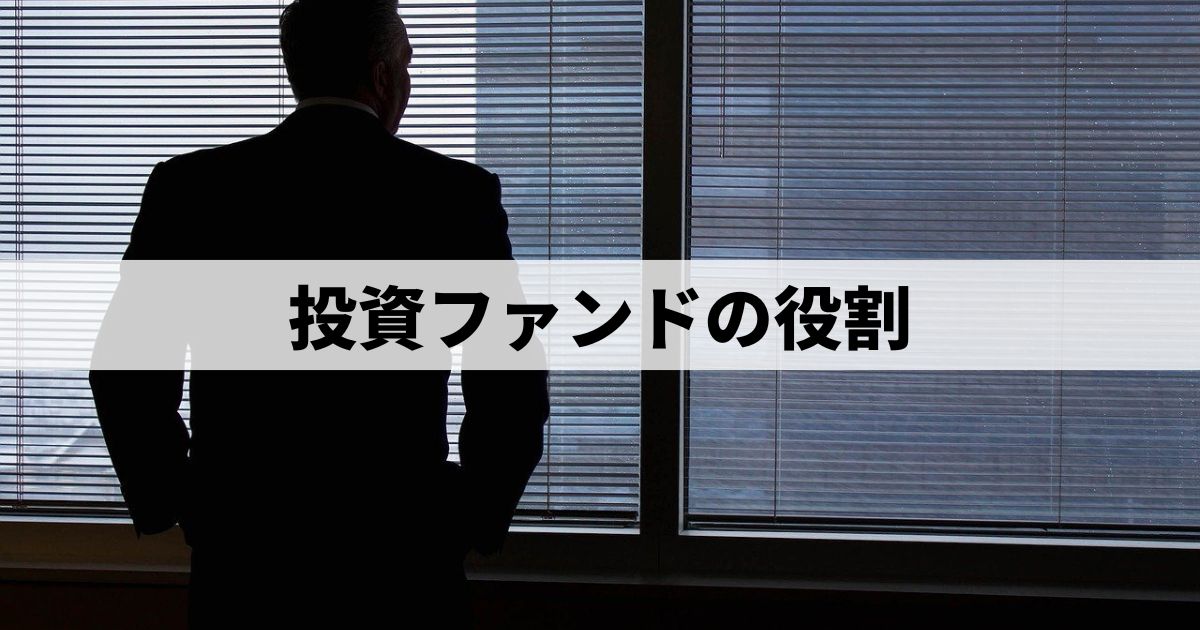
Looopによる四つ葉電力と新潟県民電力のM&A
電力小売事業、電力小売事業に関わる各種業務委託業、太陽光発電所システムの開発・販売・設置・工事・管理・メンテナンスなどを手掛けるLooopは、デンタルケア製品の開発・製造・販売などを手掛ける歯愛メディカルから四つ葉電力株式会社と新潟県民電力株式会社の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年6月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:電力小売事業の拡大
AbalanceによるBLESSのM&A
グリーンエネルギー事業、建設機械事業、IT事業などを手掛けるAbalanceは、子会社であるバローズを通じて、太陽光等を利用した発電業務及び電力の販売などを手掛けるBLESSの全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年3月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:2億8,100万円
- 目的:ストック型ビジネスの推進
藤井産業による帯広ソーラーパークのM&A
電設資材、電気機器、工作機械、情報機器、土木建設機械等の販売などを手掛ける藤井産業は、太陽光発電事業を営む帯広ソーラーパークの全持分を取得し、子会社化しました。
- 実行時期:2020年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:10万円
- 目的:メガソーラー発電所のノウハウ獲得


東京ガスによる大規模太陽光事業のM&A
都市ガス・LNG販売事業、電力事業、エネルギー関連事業を手掛ける東京ガスは、米国で再生可能エネルギー開発事業を手掛けるヘカテエナジーからテキサス州にある大規模太陽光事業を譲り受けました。
- 実行時期:2020年8月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:太陽光発電事業の海外進出

高島による新エネルギー流通システムのM&A
建材などを取り扱う多角的専門商社の高島は、太陽光発電システム関連・オール電化システム工事を手掛けている新エネルギー流通システムを子会社化しました。
- 実行時期:2022年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:工事施工の機能強化
パワーでんきイノベーションによるパワーでんきカンパニーの太陽光設備事業のM&A
電気工事や蓄電池システム販売などの事業を行うパワーでんきイノベーションは、太陽光発電設備の販売施工等行っているパワーでんきカンパニーの太陽光設備に係る事業を譲り受けました。
- 実行時期:2022年12月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:建設現場で使うエネルギーの自然エネルギーへの転換
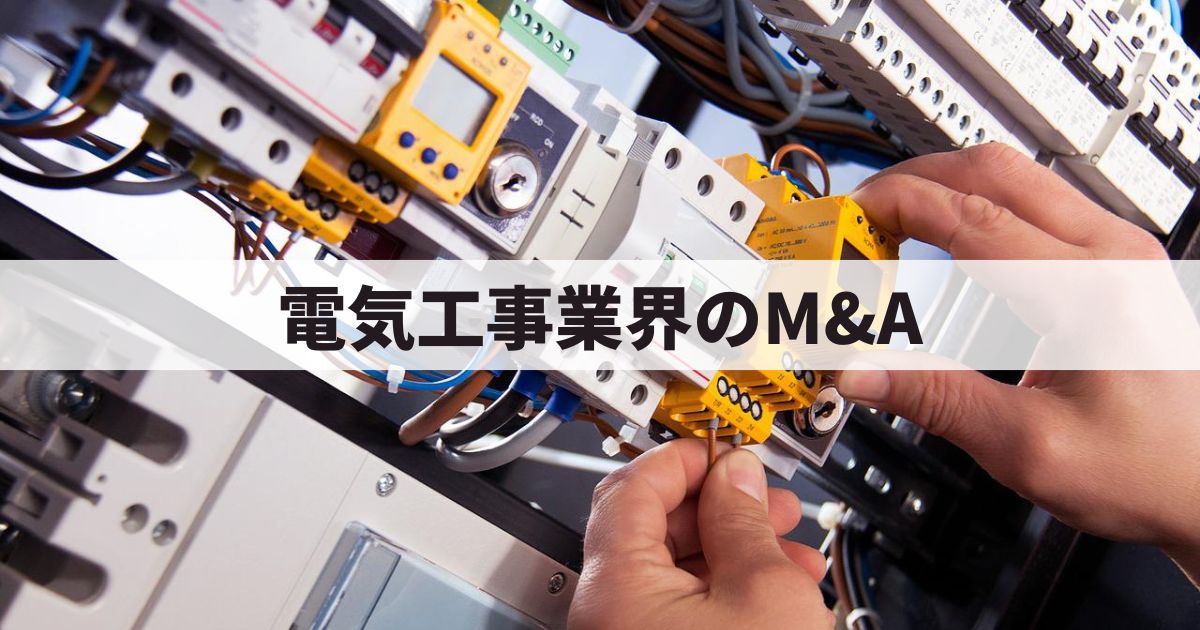
RVHによるBS ENERGYのM&A
システム開発などを行う事業子会社の管理などを行うRVHは、営農型太陽光発電所の企画、設計等を行っているBS ENERGYを子会社化しました。
- 実行時期:2022年9月
- スキーム:株式交換
- 取引価額:1億7,000万円
- 目的:新たな再生可能エネルギー事業の開始
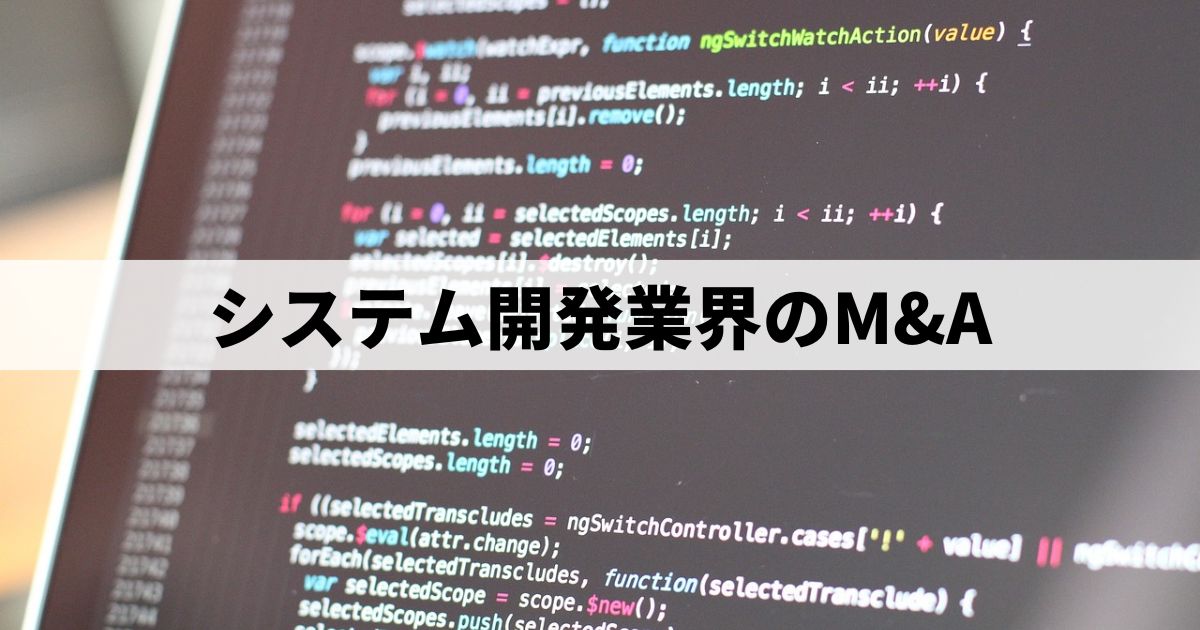
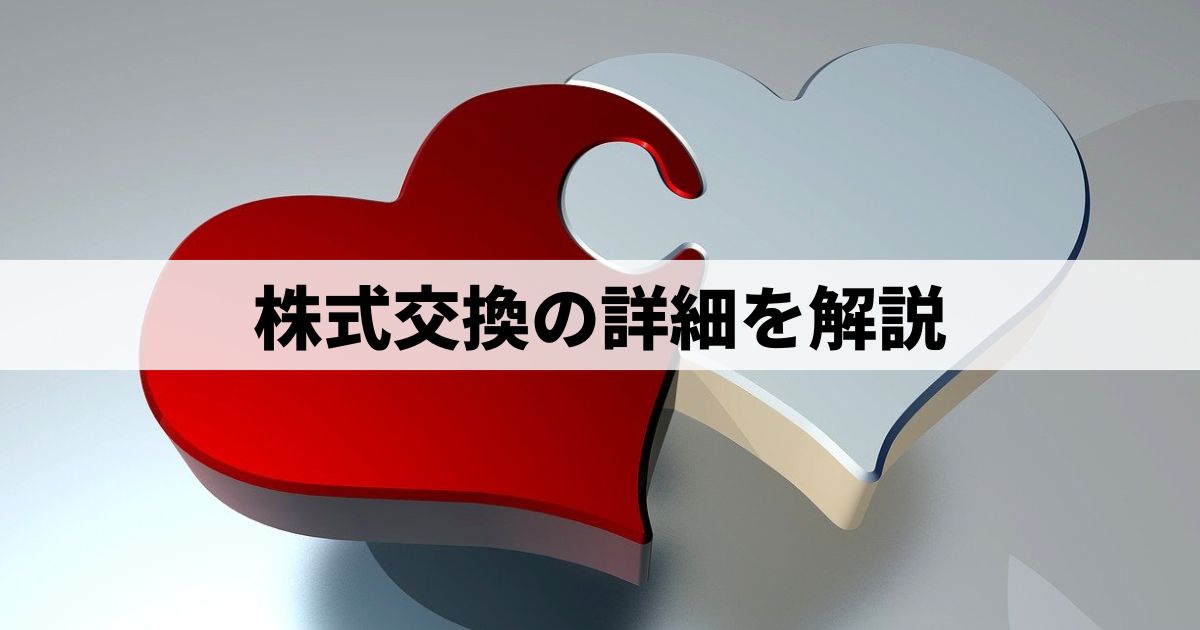
シーラホールディングスによる日本太陽光発電のM&A
不動産売買やベンチャー投資などの事業を展開しているシーラホールディングスは、太陽光発電の設計、施工等を行っている日本太陽光発電を子会社化しました。
- 実行時期:2022年02月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:太陽光設備を完備した自家発電のマンション開発

エネプライムによるオランジュのM&A
自然エネルギーに関する設備等の販売などを行うエネプライムは、高圧太陽光メンテナンスなどを手掛けるオランジュを子会社化しました。
- 実行時期: 2021年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:経営資源の半導体検査装置事業への集中化
バローズによるカンパニオソーラーのM&A
発電所の設計・建設・運営および運営に関するコンサルティングなどを行うバローズは、 太陽光発電事業を営む株式会社カンパニオソーラーを買収しました。
- 実行時期:2021年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:7億3,200万円
- 目的:安定収益とキャッシュ・フローの確保
ハイアス・アンド・カンパニーによるOMソーラーのM&A
住宅・不動産業界のコンサルティングを行うハイアス・アンド・カンパニーは、パッシブデザインを軸に事業を展開しているOMソーラーを子会社化しました。
- 実行時期:2022年11月
- スキーム:第三者割当増資
- 取引価額:2億7,030万円
- 目的:会員企業向けビジネスの発展
タカラレーベンによるACAクリーンエナジーのM&A
マンションや戸建て住宅の開発を手掛けるタカラレーベンは、小規模太陽光発電施設開発事業を全国で展開するACAクリーンエナジーを子会社化しました。
- 実行時期: 2021年04月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:再生可能エネルギー発電・供給事業のさらなる拡大
日本コンベヤによる関西電機工業のM&A
太陽光発電事業などを手掛ける日本コンベヤは、太陽光発電事業に技術的な強みを持つ関西電機工業を子会社化しました。
- 実行時期:2019年11月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:シナジー効果創出
日本再生可能エネルギーによるケーピーエネルギーのM&A
太陽光発電事業を行っている日本再生可能エネルギーは、く太陽光発電所の建設を進めているケーピーエネルギーを子会社化しました。
- 実行時期:2019年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:39億1,600万円
- 目的:経営資源の商品販売事業と工事事業への集中化
ダイキアクシスによるメデアのM&A
水回りの住宅関連商材など「水」を軸とした事業を展開しているダイキアクシスは、太陽光発電設備を中心とした電気工事業を行っているメデアを子会社化しました。
- 実行時期:2023年2月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:取引先ネットワーク・商圏の拡大
ナックによるエースホームとナックスマートエネルギーのM&A
ダスキン事業を中核とするレンタル事業を展開するナックは、住宅フランチャイズ企業のエースホームと、太陽光発電システム事業などを行うナックスマートエネルギーの間で吸収合併を行いました。
- 実行時期:2023年4月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:脱炭素社会へ向けたサービス提供の推進
東急不動産によるシン・エナジーのM&A
総合不動産企業である東急不動産と、太陽光・バイオマス・バイオガス・水力・風力・地熱発電事業を行う電源開発事業などを行うシン・エナジーは、資本業務提携をしました。
- 実行時期: 2022年12月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:再エネ発電所の開発力強化による再エネ事業の領域拡大
関西電力によるリニューアブル・ジャパンのM&A
電気通信事業、ガス供給事業等を行っている関西電力は、太陽光発電事業・ 風力発電事業等を行っているリニューアブル・ジャパンと資本業務提携をしました。
- 実行時期:2020年07月
- スキーム:第三者割当増資
- 取引価額:非公開
- 目的:共同開発・獲得・運営、人員派遣の業務提携
サンフロンティア不動産によるノータスソーラージャパンのM&A
不動産再生と活用サービスに強みを持つサンフロンティア不動産は、営農型太陽光発電事業を手掛けているノータスソーラージャパンと資本業務提携をしました。
- 実行時期:2023年3月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:年間3億キロワットアワー以上の発電
日本電計による新栄電子計測器のM&A
電子計測器や電子部品などの事業を展開する日本電計は、太陽光発電所システムやメガソーラー事業を展開する新栄電子計測器を子会社化しました。
- 実行時期:2020年1月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:業容拡大
あいおいニッセイ同和損害保険によるウエストホールディングスのM&A
損害保険事業を行っているあいおいニッセイ同和損害保険は、太陽光発電を主力とした事業を展開するウエストホールディングス と資本業務提携契約をしました。
- 実行時期: 2022年06月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:カーボンニュートラルに向けた取り組みの共同開発

JERAによるザライ電力のM&A
電気事業、ガス事業などを行っているJERAは、再生可能エネルギー発電事業者のザライ電力を子会社化しました。
- 実行時期: 2022年08月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:再生可能エネルギープロジェクトの共同開発
三井物産によるSolstice Power Technologies, IncのM&A
米国エネルギー・サステナビリティ関連事業開発に注力している総合商社の三井物産は、米国のコミュニティソーラー事業者向けにサービスを提供しているSolstice Power Technologies, Incを子会社化しました。
- 実行時期:2022年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:分散型太陽光事業を含む米国エネルギー・サステナビリティ関連の事業開発
オリックスによるElawan Energy S.L.のM&A
リース事業をはじめ法人金融など多角的に事業を展開するオリックスは、スペインを中心に太陽光発電所の開発・運営を行っているElawan Energy S.L.を完全子会社化しました。
- 実行時期:2022年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:国内外での設備容量合計10GWまでの拡大

丸紅によるChenya Energy Co., Ltd.のM&A
世界19カ国で発電資産を保有・運営する丸紅は、台湾にて太陽光発電事業の開発、建設、保守・運転を行うChenya Energy Co., Ltd.を子会社化しました。
- 実行時期:2020年02月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:再生可能エネルギー事業開発の基盤強化
北海道電力によるAlten RE Developments America B.V.のM&A
電力供給を担う北海道電力は、メキシコにおいて太陽光発電所の運営を行っているAlten RE Developments America B.V. を子会社化しました。
- 実行時期: 2020年04月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:メキシコ合衆国における太陽光発電所の運営参画
東京ガスアメリカによるカテエナジーの大規模太陽光事業のM&A
東京ガスの北米新規事業への投資および運営管理を行っている東京ガスアメリカは、再生可能エネルギー開発事業者のカテエナジーより大規模太陽光事業を譲り受けました。
- 実行時期:2020年8月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:国内外での再生可能エネルギー電源取扱量500万kWの獲得
おわりに
本記事のまとめ
太陽光発電業界の市場動向、M&A動向、買収事例についてご紹介しました。
太陽光発電業界は、FIT法・FIP法・省エネ法などの施行、改正により、これまで収益機会や収益構造が大きく変化してきた業界です。
法改正の内容次第で他社資本や設備との連携が必要な状況が多々出てくることから、今後も業界内のM&Aはますます活発化すると見込まれています。
M&A・事業承継のご相談はハイディールパートナーズへ
M&A・事業承継のご相談は経験豊富なM&Aアドバイザーの在籍するハイディールパートナーズにご相談ください。
ハイディールパートナーズは、中堅・中小企業様のM&Aをご支援しております。弊社は成約するまで完全無料の「譲渡企業様完全成功報酬型」の手数料体系を採用しており、一切の初期費用なくご活用いただけます。
今すぐに譲渡のニーズがない企業様でも、以下のようなご相談を承っております。
- まずは現状の自社の適正な株式価値を教えてほしい
- 株式価値を高めるために今後何をすればよいか教えてほしい
- 数年後に向けて株式価値を高める支援をしてほしい
- どのような譲渡先が候補になり得るか、業界環境を教えてほしい
ご相談は完全無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。


