倉庫業界の業界動向、M&A・売却・買収事例30選

倉庫業界は近年M&Aが活発な業界の一つです。倉庫業界は、EC利用が拡大したことで今後も引き続き需要の高まりが期待される業界です。
本記事では、そうした倉庫業界の市場動向を解説するとともに、倉庫業界におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。
倉庫業界の概要・市場動向
倉庫業界とは
倉庫業界とは、寄託を受けた荷物を倉庫において補完する業界をいいます。
かつては国土交通省の認可による許可制が採用されていましたが、2022年からは倉庫管理責任者を選任したうえで国土交通省の登録を受けることが義務付けられています。
業務内容は場所の賃貸に限らず、検品、在庫管理、流通加工、通関業務、受注発注なども含んでいるため、運送業と並んで物流の中核と見なされています。

倉庫業界の市場動向
倉庫需要の拡大
EC拡大の恩恵を受けて、倉庫業界の市場規模は拡大しています。
国土交通省「第11回全国貨物純流動調査(物流センサス)の調査結果(速報)」によると、全国貨物純流動量は2015年から2021年にかけて8.2%減少していますが、倉庫業だけは15.4%の増加を記録しています。
出荷1件当たりの貨物量は2015年には1.73トンでしたが2021年には1.09トンまで減少しており、小ロット化が進行しています。これは消費者が物品の大きさにかかわらずECを利用する機会が増加していることを反映していると推測されます。
今後もこの傾向がは継続するため、商品を保管・管理する倉庫業界にとっては追い風になっています。
倉庫の自動化・機械化
倉庫業界では、労働力不足や業務の効率化を目的に自動化・機械化が進行しています。
リストや注文書をもとに指定の品物を集めるピッキングや、箱やケースをパレットに積上げるパレタイズにロボットを活用するほか、無人フォークリフトや無人搬送車が導入されています。
また、倉庫の利用者と提供者のマッチングを効率的に行って物流施設の遊休スペースを最小化する倉庫シェアリングには、物流の最適化において大きな役割が期待されています。
これらの導入には相応の資金が必要ですが、倉庫業界は中小企業が大半を占めているため資金を用意できない事業者も存在します。
この業界構造はシェアを拡大したい大手企業からすると、買収を通じて売り手の業務効率化を推進できる余地が大きいと言えます。
そのため、国が「自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業」として支援策を講じるといったことや、中小事業者の機械導入事例を表彰して金融支援を行うなどの取り組みがなされています。
倉庫事業の多機能化
近年の倉庫業界では、産業構造の変化や物流施設に求められる役割の変化を背景に、倉庫の総合化・高機能化が進行しています。
バブル崩壊以降、企業の生産拠点が海外に移されたことで企業が資産圧縮を推し進めた結果、倉庫事業を始め物流事業が外部委託されるようになりました。
倉庫事業者も、在庫の最適化やリードタイムの縮小などサプライチェーンを最適化したい企業の要求に応えるために、保管機能に対応した保管型倉庫から、大規模なフロア面積に多数のバース(荷物の積卸のためにトラックを停車する場所)を備えるスルー型の物流センターへとシフトしました。
高機能化の代表的な例が3PL(3rd Party Logistics)です。3PLとは、荷主企業に代わって第三者が効率的な物流システムを提案したり、物流業務の企画・設計・運営を包括して請け負う業態を指します。
3PL事業は国土交通省も推進しており、国土交通省「物流:3PL事業の総合支援」では、人材育成推進事業の実施、ガイドライン等の策定、税制特例などの支援が明記されています。
倉庫業界のM&A動向
倉庫業界では、大規模な拠点網を有する大手事業者と中小事業者間でのM&Aが活発です。
倉庫業界の大手4社のシェアは10%程度であるため、輸送網を拡大することで物流ビジネスの最適化を図る大手事業者と機械化により業務の効率化を図りたい中小事業の間での業界再編が加速しています。
国内市場の物流量が減少していることを受けて海外市場へ展開する倉庫会社も増加しているほか、荷主企業である製造企業などが保有する物流会社を倉庫会社へ売却する事例も見られます。
倉庫業界におけるM&Aのメリット
売り手のメリット
倉庫業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。
- 大手事業者の資本を活用して設備投資を実行できる
- 自動化・機械化を実現することで業務を効率化できる
- 買い手の3PL事業に組み込まれることで多様なサービスを提供できる
- 後継者が不在の場合、廃業せず事業を継続し社員の雇用を守ることができる
- 後継者問題を解決し、株式譲渡による譲渡収入とともに経営から退くことができる
- M&Aを契機に代表者による借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
倉庫業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。
- 売り手の保有する輸送網・拠点網を拡大できる
- 売り手の倉庫や設備をそのまま活用できる
- 売り手の抱える経験のある人材を確保できる
- 売り手の顧客網を取り込むことができる
- 業界内でのシェア拡大に繋げることができる
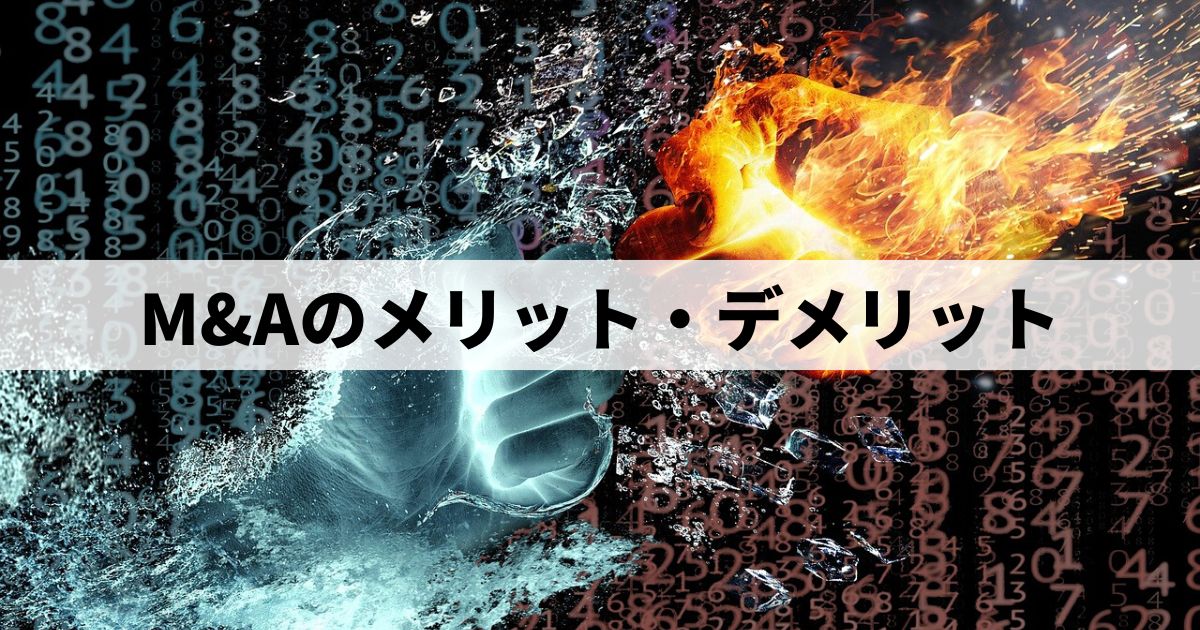
倉庫業界のM&A・売却・買収事例
国分ロジスティクスによる中島運送のM&A
一般貨物自動車運送業、軽貨物運送事業等の物流事業、倉庫事業などを手掛ける国分ロジスティクスは、東京都世田谷区を拠点に、一般区域貨物自動車運送を手掛ける中島運送の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年9月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:首都圏エリアでの配送機能の強化
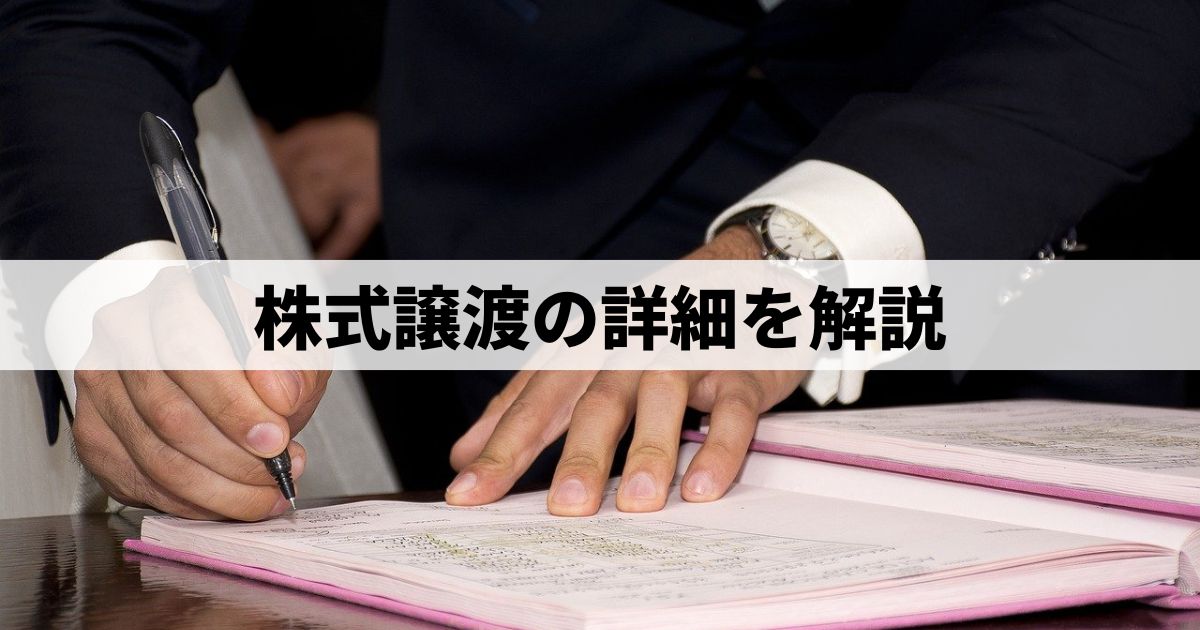
セイノーホールディングスによる丸久運輸のM&A
国内・国際輸送、冷凍倉庫、食品宅配、引越などを手掛けるセイノーホールディングスは、食品・飲料関係を中心とした常温・冷蔵・冷凍倉庫業、物流加工業、輸送業を展開し、近年は3LP事業や物流コンサルティング事業を手掛ける丸久運輸の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年8月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:低温流通網の拡充

廣済堂によるエヌティとNeoのM&A
情報ソリューション事業、人材サービス事業、エンディング関連事業を手掛ける廣済堂は、物流倉庫業への人材派遣業を手掛けるエヌティとNeoの全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:情報ソリューション事業や BPO 事業等との連携
SBSホールディングスによる東洋運輸倉庫のM&A
総合物流事業、オフィス・住居・物流施設の不動産賃貸・開発事業などを手掛けるSBSホールディングスは、東京臨海部などで倉庫・通関・運送業を手掛ける東洋運輸倉庫の全株式得を取得しました。
- 実行時期:2021年1月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:最先端倉庫の開発・拡大
福岡運輸によるオー・ケー・ラインのM&A
定温物流・倉庫業、不動産賃貸業、港湾運送・通関業などを手掛ける福岡運輸は、食品小口配送に特化した定温物流・倉庫業を手掛けるオー・ケー・ラインの全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年1月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:物流拠点の拡大
センコーによるナガセ物流のM&A
括的な物流サービスを手掛けるセンコーは、化学系大手専門商社長瀬産業の子会社で、主に長瀬産業グループが取り扱う製品(化学品や樹脂など)の保管・輸送・流通加工事業を手掛けるナガセ物流の株式過半数を取得しました。
- 実行時期:2020年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:化学物流業界における認知度向上

トナミホールディングスによる新生倉庫と御幸倉庫のM&A
3PL事業を展開する企業グループの持株会社であるトナミホールディングスは、主に中国エリアで食品メーカー系物流を強みとして倉庫業・運送業などをてがける新生倉庫の株式67%と、主に中部エリアでメーカー系物流を強みとして倉庫業・運送業などをてがける御幸倉庫の全株式をそれぞれ取得しました。
- 実行時期:2020年7月(新生倉庫)、2020年12月(御幸倉庫)
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:生産性の向上
岡崎通運による大昭運輸のM&A
一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業などを展開している岡崎通運は、一般貨物運送自動車運送業、倉庫業、荷役梱包業を行っている大昭運輸を子会社化しました。
- 実行時期:2021年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:最適なサプライチェーン実現と事業拡大

坂出ユタカサービスによる坂出事業所のM&A
坂出事業所の委託を受けている坂出ユタカサービスは、営業倉庫・サイロにおける倉庫業、不動産業等を担っているJ-オイルミルズの坂出事業所より事業を譲り受けました。
- 実行時期:2019年12月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:20億円
- 目的:選択と集中及び効率化の実現
日新による日新エアカーゴのM&A
国際・国内輸送、倉庫等の事業を行っている日新は、航空貨物混載運送取扱業や、倉庫流通加工業を行う日新エアカーゴを吸収合併をしました。
- 実行時期:2024年4月1日
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:部門全体の効率化

manabyによる奥洲物産運輸のM&A
障害者就労支援事業所を展開・運営しているmanabyは、一般貨物自動車運送事業・倉庫業と共に就労移行支援も行う奥洲物産運輸より事業を譲り受けました。
- 実行時期:2023年1月1日
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:6,000万円
- 目的:関東エリアでのサービス拡大、就労移行支援のノウハウを持つ人材の承継を通じた事業成長
丸和運輸機関によるM・KロジのM&A
埼玉県に本社を置く物流企業の丸和運輸機関は、倉庫業、物流アウトソーシング、物流コンサルティング事業を行っているM・Kロジを子会社化しました。
- 実行時期:2022年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:D2C事業者向けの3PLノウハウを有するM・Kロジとともに、EC物流事業における機能強化
日清製粉による熊本製粉のM&A
業務用の小麦粉、および関連商材の製造・販売を行っている日清製粉は、製粉業、加工食品業、倉庫業、不動産業などを行う熊本製粉を子会社化しました。
- 実行時期:2022年06月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:コスト競争力と市場への適応力強化

日本物流未来投資事業有限責任組合によるEMCのM&A
中堅・中小物流事業者を支援する投資組合の日本物流未来投資事業有限責任組合は、物流設計、倉庫手配、人員手配等の物流サービスを展開しているEMCより株式を譲渡しました。
- 実行時期:2022年05月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:EMCの更なる事業拡大・競争力の強化
マルハニチロによるマリンアクセスのM&A
幅広く食品の加工・販売事業等を展開しているマルハニチロは、マグロを主とする水産物の調達、加工、冷凍保管等を手掛けるマリンアクセスをグループ化しました。
- 実行時期:2021年9月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:マグロ事業の更なる拡充の実現と、顧客先へのさらなるサービスの提供
サントリー食品インターナショナルによる九州サンベンドのM&A
清涼飲料の製造・販売を行っているサントリー食品インターナショナルは、飲料関連機材の整備・保管を行っている九州サンベンドを吸収合併しました。
- 実行時期:2023年6月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:グループの機材整備事業の再編
ヤマタネによるシンヨウ・ロジのM&A
物流、食品、情報、不動産事業を展開しているヤマタネは、生鮮・食品などの一般貨物運送事業および倉庫事業などを行っているシンヨウ・ロジを子会社化しました。
- 実行時期:2022月4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:物流事業および食品事業との事業シナジー創出
ルセット・ナインによるマルシェマシナリーの一部事業のM&A
新冷却技術の「TT-Box©︎シリーズ」事業を展開するルセット・ナインは、急速冷凍装置事業等を行っているマルシェマシナリーより一部事業を譲り受けました。
- 実行時期:2021年12月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:「高電位電圧技術」を活用した次世代型鮮度保持システムの開発・製造・販売・メンテナンスまで一貫して行う体制の構築
大和ハウス工業による神山運輸のM&A
戸建住宅、賃貸住宅などの事業を行っている大和ハウス工業は、常温・冷蔵・冷凍も行う低温物流会社の神山運輸を株式交換により子会社化しました。
- 実行時期:2022年9月
- スキーム:株式交換
- 取引価額:非公開
- 目的:低温物流事業の拡大と、協業による物流事業の拡大
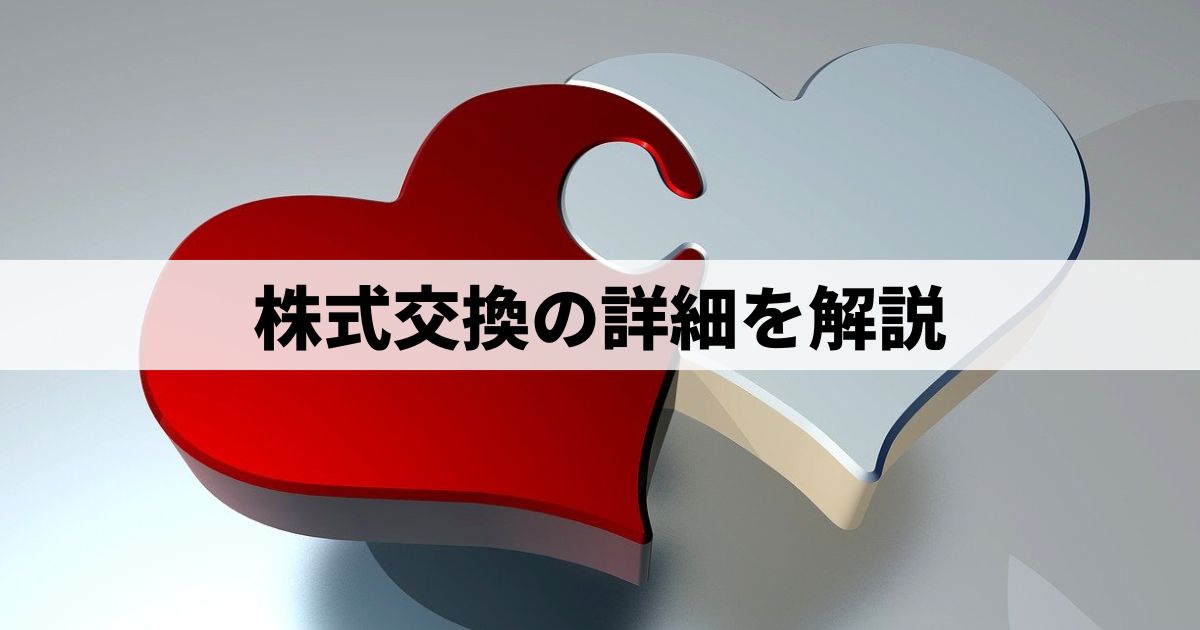
大東建託によるエアトランクのM&A
総合賃貸業を核とする大東建託は、集荷・配送無料の宅配型トランクルーム『エアトランク』を運営するエアトランクと資本業務提携をしました。
- 実行時期: 2019年11月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:建設・不動産事業の強化、リユース・シェアサービスへの事業展開
エアロネクストによるセイノーHDのM&A
産業用ドローンの研究開発等をするエアロネクストは、貨物自動車運送事業や倉庫業などを行っているセイノーHDと資本業務提携をしました。
- 実行時期:2021年06月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:リーズナブルな価格の機体提供および機体の安定供給体制の構築
ファイズホールディングによるブリリアントトランスポートのM&A
人材紹介業を行うファイズホールディングは、通関取扱業務、配送業務等を展開しているブリリアントトランスポートを子会社化しました。
- 実行時期:2021年4月
- スキーム:第三者割当増資
- 取引価額:1,800万円
- 目的:グループのロジスティクスサービス事業との連携強化

南日本運輸倉庫による和幸流通サービスのM&A
冷凍・冷蔵の物流をメインに運送サービスを展開する南日本運輸倉庫は、輸送や、最適な倉庫のロケーションを提案している和幸流通サービスを子会社化しました。
- 実行時期:2022年07月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:さらなる品質の向上、効率化、サービス向上
キユーソー流通システムによるKIAT ANANDAグループのKACS、AS、MKA、TKSの4社のM&A
倉庫業、各種瓶缶詰類その他一般物品の包装事業などをを展開しているキユーソー流通システムは、倉庫事業や運送事業を手掛けるKIAT ANANDAグループのKACS、AS、MKA、TKSの4社を子会社化しました。
- 実行時期:2020年9月
- スキーム:第三者割当増資
- 取引価額:約70億円
- 目的:インドネシア市場における高品位な低温物流サービスの提供と物流ネットワーク構築
センコーグループホールディングスによるAirRoad Pty LtdのM&A
物流、商事、ビジネスサポート等の事業を展開しているセンコーグループホールディングスは、貨物自動車運送事業、倉庫事業を行うAirRoad Pty Ltdをグループ化しました。
- 実行時期: 2021年04月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:3PL事業拡大、コールドチェーン事業への本格参入
みずほリースによるMAC Trailer Leasing, Inc.の株式取得
海外アセットファイナンスでの協業等に取り組むみずほリースは、米国にて冷凍・冷蔵トレーラーリース・レンタル事業を行うMAC Trailer Leasing, Inc.の持分の50&を丸紅より譲り受けました。
- 実行時期:2020年3月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:約159億円
- 目的:事業基盤の一層の拡充ならびにグローバル市場におけるプレゼンス向上
国分グループ本社による上海恒孚物流有限公司のM&A
酒類・食品・関連消費財の流通加工事業等を展開する国分グループ本社は、倉庫業務および配送業務を行う中国の上海恒孚物流有限公司を子会社化しました。
- 実行時期:2021年07月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:華西エリアへの物流事業の拡大
ニチレイロジグループによるKevin Hancock LimitedのM&A
低温物流事業を担っているニチレイロジグループは、冷凍・チルド食品の保管、急速凍結サービスの提供等を行っているKevin Hancock Limitedを子会社化しました。
- 実行時期:2023年01月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業の更なる拡大
ニチレイロジグループ本社によるNLCCNのM&A
低温物流事業を担っているニチレイロジグループ本社は、冷蔵・冷凍倉庫業、利用運送業を行っているNL COLD CHAIN NETWORK(M)SDN. BHD.を子会社化しました。
- 実行時期:2023年2月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:マレーシア事業のさらなる拡大
日本通運によるMD Logistics, Inc.およびMD Express, Inc.のM&A
航空貨物輸出入などを行う日本通運は、医療薬品産業向け物流事業を主とするMD Logistics, Inc.およびMD Express, Inc.を子会社化しました。
- 実行時期:2020年9月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:米国内の医療品物流ネットワーク獲得
おわりに
本記事のまとめ
倉庫業界の市場動向、M&A動向、買収事例についてご紹介しました。
倉庫業界は、国内物流量の減少に反して、EC化の進展により需要が拡大している業界です。
現在では倉庫に求められる役割が保管機能に留まらず在庫管理や受発注データの管理など多岐に渡るため、物流網の中でも欠かせない存在になっています。
今後は業務の効率を追求するために機械化・自動化が進行するため、設備投資を行うことができない事業者を対象としたM&Aが加速すると見込まれます。

M&A・事業承継のご相談はハイディールパートナーズへ
M&A・事業承継のご相談は経験豊富なM&Aアドバイザーの在籍するハイディールパートナーズにご相談ください。
ハイディールパートナーズは、中堅・中小企業様のM&Aをご支援しております。弊社は成約するまで完全無料の「譲渡企業様完全成功報酬型」の手数料体系を採用しており、一切の初期費用なくご活用いただけます。
今すぐに譲渡のニーズがない企業様でも、以下のようなご相談を承っております。
- まずは現状の自社の適正な株式価値を教えてほしい
- 株式価値を高めるために今後何をすればよいか教えてほしい
- 数年後に向けて株式価値を高める支援をしてほしい
- どのような譲渡先が候補になり得るか、業界環境を教えてほしい
ご相談は完全無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。


