飲食・外食業界の業界動向、M&A・売却・買収事例30選

飲食・外食業界は近年M&Aが活発な業界の一つです。コロナ禍によって飲食業界は厳しい状況にあり、多くのM&Aが行われています。
本記事では、そうした飲食・外食業界の市場動向を解説するとともに、飲食・外食業界におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。
飲食・外食業界の概要・市場動向
飲食・外食業界とは
飲食・外食業界とは飲食店を営む事業者を指し、食品衛生法に定められる「食品等事業者」の一種に当たります。
飲食店営業を行う場合は飲食営業許可が必要になり、都道府県知事が定める製造施設・製造設備などの基準に適合しなければならず、保健所で基準等の確認が必要です。
飲食・外食業界は競合が多く、競争が激しいことが特徴です。また店舗管理、接客対応、メニュー開発など様々なスキルが求められる業態です。
そのため、調理スキルだけでは生き残りは難しく、いかに他店との差別化を図るかが重要になっています。


飲食・外食業界の市場動向
深刻な人手不足
飲食・外食業界は深刻な人手不足に陥っています。
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」(2022年7月)によると73%の飲食店が人手不足であると言われています。他の多くの業界も人手不足で苦しんでいますが、飲食店は特にこの傾向が顕著です。
理由としては、24時間365日営業の店舗も多いため長時間労働に陥りやすく、また休みも取りにくいといったイメージにより、採用が難しくなっていることが挙げられます。
また人手が不足しているため一人当たりの労働量が増え、離職率が高くなってしまうといった悪循環が起きているケースも少なくありません。
新型コロナウイルスによる業績悪化
飲食業界はもっともコロナ禍の影響を受けている業界の一つです。
帝国データバンク「新型コロナウイルス関連倒産動向調査」によると、2022年11月の時点で飲食店の倒産は667件で、業種別で最も多い倒産件数です。
コロナ禍によって宴会など、飲食店に人が集まる機会が大幅に減ったことが大きな要因です。そのため、飲食業界の中でも、酒場やビアホールの倒産件数が多くなっています。
対して、テイクアウトやデリバリーの需要は堅調なため、これらの需要を取り込めるかが重要になっています。
原材料の高騰によるコスト増
コロナ禍やウクライナ侵攻、円安の影響で食材価格の高騰が進んでいます。
飲食店リサーチによる『「原材料の価格高騰」に関するアンケート調査』によると、原材料費の高騰が店舗運営に影響していると答えた飲食店は9割を超えました。
特に影響を及ぼしている食材として、小麦や食用油が挙げられました。
近年はスマホで簡単に他店との比較が可能なため、原材料費が上がっても簡単に値上げしにくい状況です。原材料費が高騰してもなるべく商品の価格を上げないように、飲食店は様々な努力を強いられています。
飲食・外食業界のM&A動向
コロナ禍だけでなく、人手不足や材料費の高騰など、飲食業界は厳しい状況に置かれています。
そのため、大手企業の傘下に入ることでブランド力やノウハウを活かし、安定した経営を行うべくM&Aを実施する事業者が増えています。
また、同業とM&Aをすることで店舗拡大や新メニューの開発を図るケースもあります。
少子高齢化により日本の飲食業界の市場は今後縮小していくと考えられ、飲食業界は参入障壁が低く競合も多いことから、海外市場への参入を考え海外企業とのM&Aを行う大手企業も増えています。
飲食・外食業界におけるM&Aのメリット
売り手のメリット
飲食・外食業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。
- 撤退に際して発生する費用や原状回復が不要になる
- 大手企業の傘下に入ることで安定した事業を継続できる
- 後継者が不在の場合、廃業せず事業を継続し社員の雇用を守ることができる
- 後継者問題を解決し、株式譲渡による譲渡収入とともに経営から退くことができる
- M&Aを契機に代表者による借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
飲食・外食業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。
- 新規参入する場合、売り手企業の保有するノウハウを獲得できる
- 売り手の抱える従業員を獲得し、人手不足を解消できる
- 売り手の持つ飲食店経営に必要な営業権を獲得できる
- 異なる客層の企業を買収することで、新しい客層にアプローチできる
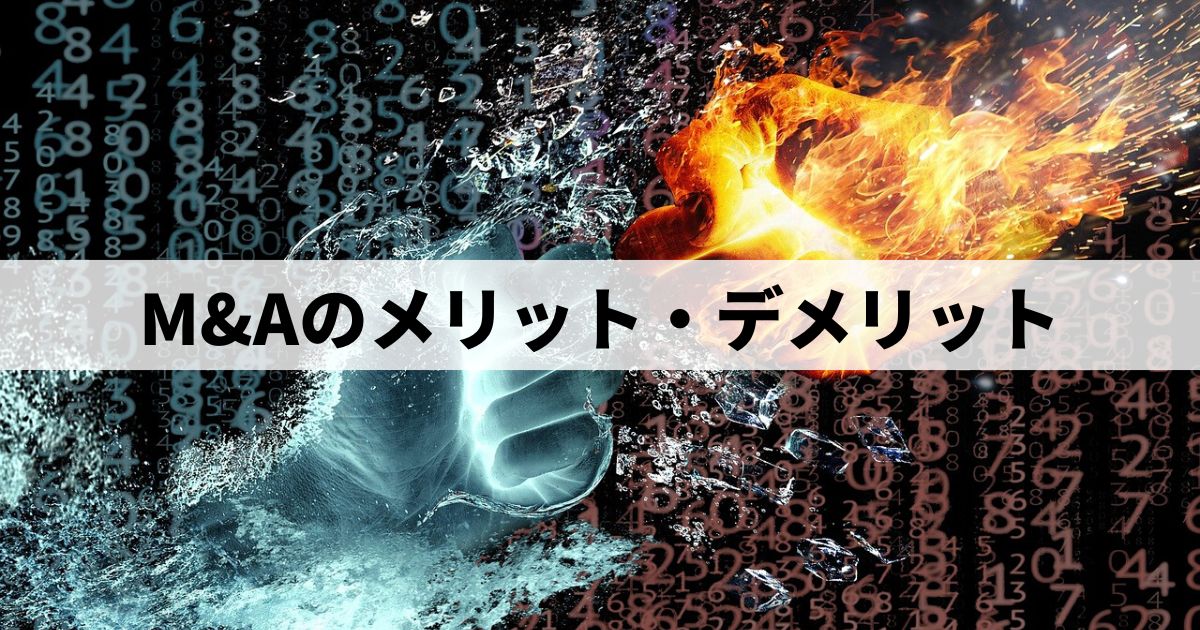
飲食・外食業界のM&A・売却・買収事例
コロワイドによるフレッシュネスのM&A
牛角やしゃぶしゃぶ温野菜を運営するコロワイドは、フレッシュネスバーガーを運営するフレッシュネスを子会社化しました。
- 実行時期:2016年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業領域の拡大
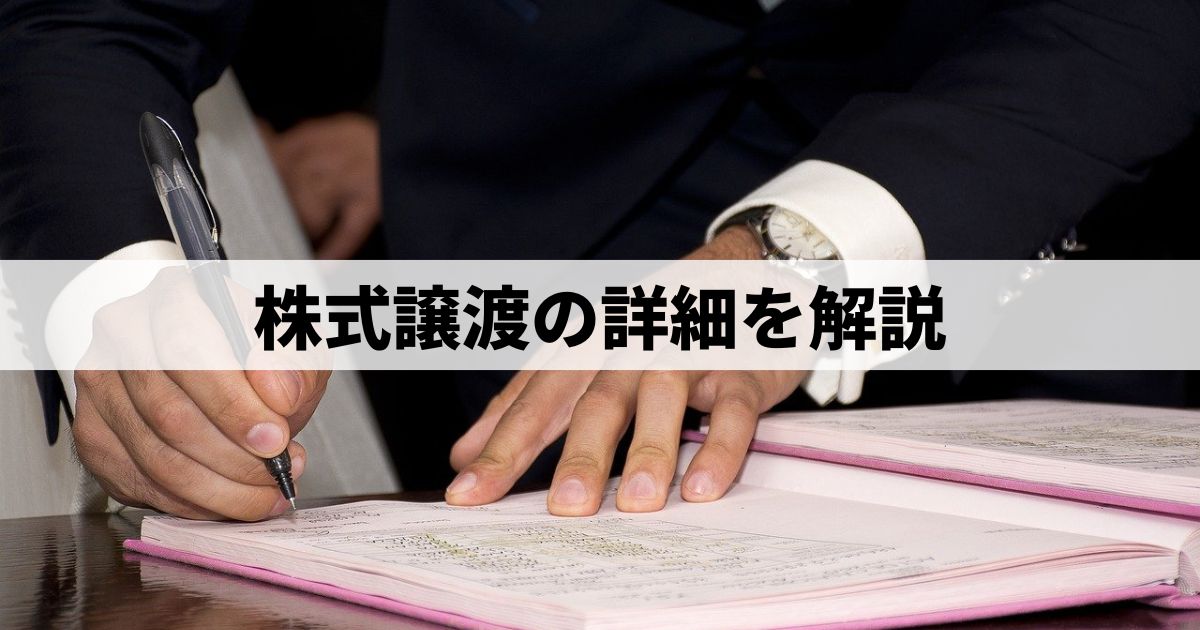
ゼンショーホールディングスによるココスジャパンのM&A
すき家を運営するゼンショーホールディングスは、ココスを運営するココスジャパンを子会社化しました。
- 実行時期:2019年11月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:新規客層の獲得
ゼンショーホールディングスによるAdvanced Fresh Concepts Crops.のM&A
すき家を運営するゼンショーホールディングスは、アメリカで持ち帰り寿司を手掛けるAFC社を子会社化しました。
- 実行時期:2018年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:海外での中食事業の展開
C-UnitedによるポッカクリエイトのM&A
全国にカフェ事業を展開するC-Unitedは、200店舗以上のカフェチェーンを運営するポッカクリエイトを子会社化しました。
- 実行時期:2022年4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:マルチブランド戦略の推進
プレナスによる宮島醤油フレーバーのM&A
ほっともっとや、やよい軒を運営するプレナスは、調味料やインスタント食品の販売を手掛ける宮島醤油フレーバーを子会社化しました。
- 実行時期:2016年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:生産コストの削減
日本KFCホールディングスとビー・ワイ・オーの資本業務提携
ケンタッキー・フライド・チキンを運営する日本KFCホールディングスは、和食チェーン店を運営するビー・ワイ・オーと資本業務提携を結びました。
- 実行時期:2018年2月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:新たな事業機会及びシナジーの獲得
WDIによるちんやのM&A
レストラン運営とブライダル事業を展開するWDIは、老舗すき焼き店のちんやの事業を継承しました。
- 実行時期:2021年8月
- スキーム:不明
- 取引価額:非公開
- 目的:ブランド力の向上
一家ホールディングスによるEgoのM&A
多業種飲食店経営やブライダル事業飲食事業を展開する一家ホールディングスは、飲食店の経営を行うEgoを子会社化しました。
- 実行時期:2022年4月
- スキーム:DES(デット・エクイティ・スワップ)
- 取引価額:19,950,000円
- 目的:事業成長
ホットランドによるファンインターナショナルのM&A
「築地銀だこ」などの飲食店事業を行うホットランドは、店舗運営事業、事業推進事業を展開しているファンインターナショナルを子会社化しました。
- 実行時期:2020年8月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:意思決定の迅速化
フライドグリーントマトによるグリーンズプラネットのM&A
飲食業トータルプランニング業務を行うフライドグリーントマトは、商業施設を中心に複数飲食店ブランドを展開しているグリーンズプラネットを子会社化しました。
- 実行時期:2022年3月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:企業価値向上
JBレストランによるハットリフーズのM&A
中華料理を主にレストランビジネスを行うJBレストランは、あんかけスパゲッティを主力としたレストランビジネスを展開するハットリフーズを吸収合併しました。
- 実行時期:2023年6月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:組織運営効率化と収益力強化

ゼンショーホールディングスによるロッテリアのM&A
すき家等をを運営するゼンショーホールディングスは、全国にファーストフードを358店舗展開しているロッテリアを子会社化しました。
- 実行時期:2023年4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業拡大
ドンクによる北欧トーキョーの店舗事業のM&A
喫茶室やレストラン営業など事業を展開しているドンクは、ベーカリー「HOKUO」の運営を行っている北欧トーキョーの10店舗を譲り受けました。
- 実行時期:2021年12月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:商業施設内の店舗開発などにおける連携
サンマルクホールディングスによるLa MadragueのM&A
サンマルクカフェを展開するサンマルクホールディングスは、「喫茶マドラグ」を展開しているLa Madragueを子会社化しました。
- 実行時期:2022年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業拡大
梅の花による梅の花サービス西日本、梅の花サービス東日本並びに梅の花サービス九州3社のM&A
梅の花は、飲食業を行っている梅の花サービス西日本、梅の花サービス東日本並びに梅の花サービス九州を吸収合併しました。
- 実行時期:2023年5月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:業務の合理化・効率化
コイサンズによるテンフォーのM&A
ベーカリー・外食店舗を展開するフードカンパニーのコイサンズは、ピザ製造および宅配、店頭販売を行っているテンフォーの株式の一部を譲り受けました。
- 実行時期:2023年01月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:経営資源の集中
ジー・テイストによる壁の穴のM&A
平禄寿司等を運営するジー・テイストは、本格イタリアン業態や讃岐うどんのチェーンを展開する壁の穴を子会社化しました。
- 実行時期:2018年9月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:店舗網の強化や業態の拡充
兼松による物語コーポレーションのM&A
電子、食糧など幅広おい商材を扱う商社の兼松は、外食事業の直営による経営とフランチャイズチェーン展開を行う物語コーポレーションを子会社化しました。
- 実行時期:2023年02月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:関係強化
石垣食品によるエムアンドオペレーションのM&A
飲料事業および珍味事業を主力とする石垣食品は、飲食店等多様な業態を取り扱うエムアンドオペレーションを子会社化しました。
- 実行時期:2019年1月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:2,550万円
- 目的:事業運営の幅の拡大

東京一番フーズによる豊田の寿司店舗事業のM&A
飲食事業を起点6次産業化を推進している東京一番フーズは、寿司店舗チェーン等の飲食店を運営する豊田より寿司店舗事業を譲り受けました。
- 実行時期:2020年06月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:水産物の調達力強化

かんなん丸によるしんしん丸のM&A
料理飲食店飲食店の経営を行っているかんなん丸は、料理飲食店の経営するしんしん丸を吸収合併しました。
- 実行時期:2022年9月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:事業全体の強化と効率化
鮒忠による柏又のM&A
食品卸売事業、割烹事業を行っている鮒忠は、創業152年の老舗料理店「小田原柏又」を持つ柏又を子会社化しました。
- 実行時期:2022年07月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:鮒忠グループの企業価値向上
センダンによるパトリオットバトンのM&A
受託給食事業を展開しているセンダンは、5店舗で外食事業を展開しているパトリオットバトンを子会社化しました。
- 実行時期:2018年8月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:新たな領域拡大

Sapporo U.S.A.,Inc.によるStone Brewing Co LLC のM&A
サッポロHDの連結子会社であるSapporo U.S.A.,Inc.は、ビール類製造販売事業・飲食店事業などを行うStone Brewing Co LLC を子会社化しました。
- 実行時期:2022年8月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:北米酒類事業のさらなる拡大

hachibei crewによるbills waikiki LLCのM&A
飲食店の経営を行っているhachibei crewは、レストランの運営などを行うbills waikiki LLCを子会社化しました。
- 実行時期: 2022年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:経営の効率化
Toridoll Holding LimitedによるToridoll and Heyi Holding LimitedのM&A
香港にて雲南ヌードルチェーン店をグループ会社化しているToridoll Holding Limitedは、香港市場における丸亀製麺の運営を行うToridoll and Heyi Holding Limitedを子会社化しました。
- 実行時期:2022年08月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:プレゼンスの向上
麦の穂によるKimly Food Products Pte. Ltd.の老舗洋菓子店事業のM&A
ビアードパパを展開する麦の穂は、洋菓子店を運営するKimly Food Products Pte. Ltd.から老舗洋菓子店「Rive Gauche Patisserie」の事業を譲り受けました。
- 実行時期:2022年09月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:店舗展開や製造面における相乗効果
トリドールホールディングスによるFulham Shore PlcのM&A
「丸亀製麺」等の飲食店の運営を行っているトリドールホールディングスは、英国を拠点にピザ業態を営むFulham Shore Plcを子会社化しました。
- 実行時期:2023年04月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業ポートフォリオの量・質の拡充
きちりホールディングスによるPT Kichiri Rizki AbadiのM&A
直営展開にて95店舗の出店を行うきちりホールディングスは、CHAVATY等のフランチャイズ展開しているPT Kichiri Rizki Abadiを子会社化しました。
- 実行時期:2019年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:3,900万円
- 目的:東南アジアエリアでのブランド展開
壱番屋による竹井のM&A
CoCo壱番屋などを経営する壱番屋は、「麺屋たけ井」を京都・大阪で8店舗経営している竹井を子会社化しました。
- 実行時期:2023年03月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:企業価値の向上
おわりに
本記事のまとめ
飲食・外食業界の市場動向、M&A動向、買収事例についてご紹介しました。
飲食業界は新型コロナウイルスの感染拡大によって大きな打撃を受けました。その後も慢性的な人手不足や、円安・不安定な海外情勢による原材料の高騰など様々な問題に悩まされています。
こうした現状を背景に、中小事業者と大手企業とのM&Aが盛んに行われています。
また、縮小が懸念されている日本の飲食市場だけでなく、海外の飲食市場に参入するために海外企業とのM&Aを行う企業も増えてきています。
M&A・事業承継のご相談はハイディールパートナーズへ
M&A・事業承継のご相談は経験豊富なM&Aアドバイザーの在籍するハイディールパートナーズにご相談ください。
ハイディールパートナーズは、中堅・中小企業様のM&Aをご支援しております。弊社は成約するまで完全無料の「譲渡企業様完全成功報酬型」の手数料体系を採用しており、一切の初期費用なくご活用いただけます。
今すぐに譲渡のニーズがない企業様でも、以下のようなご相談を承っております。
- まずは現状の自社の適正な株式価値を教えてほしい
- 株式価値を高めるために今後何をすればよいか教えてほしい
- 数年後に向けて株式価値を高める支援をしてほしい
- どのような譲渡先が候補になり得るか、業界環境を教えてほしい
ご相談は完全無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。


