建材卸売業界の業界動向、M&A・売却・買収事例30選

建材卸売業界は近年M&Aが活発な業界の一つです。建材卸売業界は、住宅市場の落ち込みとともに需要が減少している業界です。
本記事では、そうした建材卸売業界の市場動向を解説するとともに、建材卸売業界におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。
建材卸売業界の概要・市場動向
建材卸売業界とは
建材卸売業界とは、住宅設備や木材建材などのメーカーから建材や建設資材を仕入れてゼネコンや工務店などへの卸売りをする業界です。
建材は建築資材・建築材料とも呼ばれます。
建材は構造材と仕上げ材に分類され、前者は柱・梁のような建物の骨組みを構成する材料を指し、後者は建物の内外装に使用される材料で、内装材・外装材に分類されます。
内装材は壁・天井・床に使用する材料を指し、外装材はタイル・レンガ・屋根瓦などの建物外部を材料を指します。
建材卸売業では多様な建材を扱うことから、流通経路は業界内でも多重構造になっていることが一般的です。
建材卸売業界の市場動向
新築住宅市場と連動して停滞する建材需要
建材卸売市場は建材の納入先である建設業界全体の市況に左右されます。
納入先は建設会社・商業施設・工務店・デベロッパーなどが該当し、建材市場の動向は住宅市場と連動する傾向があります。
国土交通省「建築着工統計調査報告」によると、令和3年度の新設住宅着工戸数は856,484戸で、平成11年の1,212,601戸から減少傾向にあります。
マンションの着工戸数も同期間で約半数に減少しており、結果として建材の需要低下を引き起こしています。
実際、建材卸売業の商品販売額も1991年の35兆円をピークに、現在は20兆円程度まで減少しています。
リフォーム市場の開拓余地
今後の建材卸売市場の拡大には、リフォーム市場に着目した建材需要を捉えることが不可欠です。
低迷する新築住宅需要に反してリフォーム市場は一定以上の需要が期待されており、建材需要の減少を補完することができます。
国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査」によると、平成23年度のリフォーム・リニューアルの受注残高は8兆5,000億円(住宅:3兆700億円、非住宅建築物:5兆4,300億円)でしたが、平成28年度には12兆8,000億円(住宅:4兆1,500億円、非住宅建築物:8兆6,500億円)まで増加しました。
現在はコロナ禍により一時的にリフォーム需要が落ち込んでいますが、中長期的にはリフォーム市場の緩やかな拡大が期待されます。
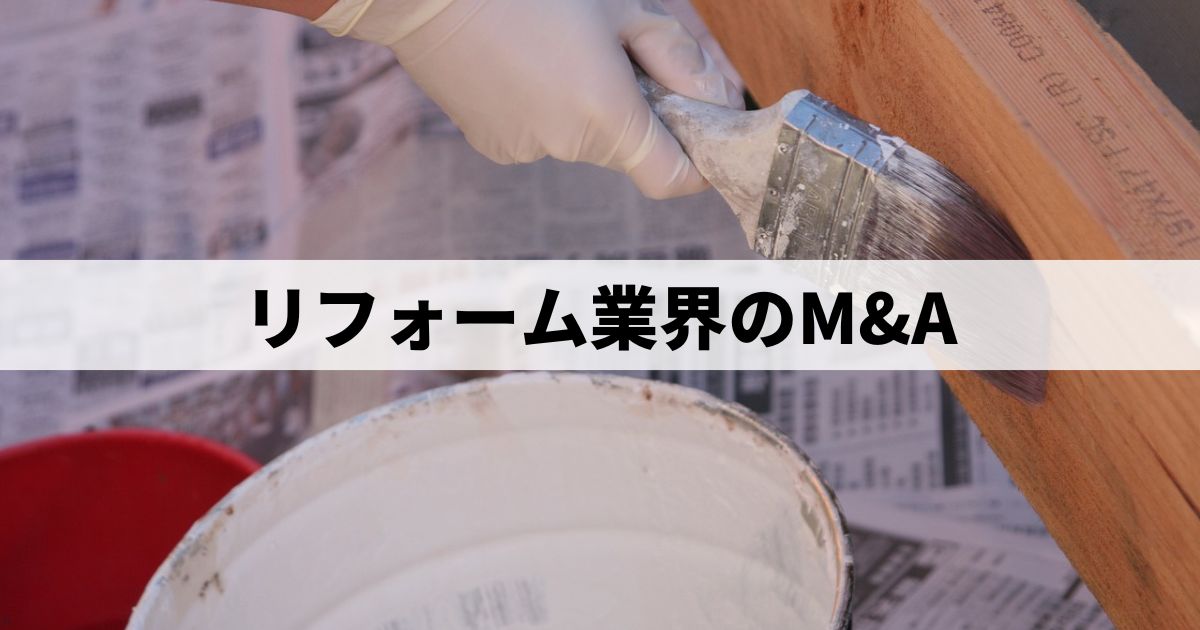
グリーン建材市場の成長
今後成長が期待できる分野として、環境に配慮したグリーン建材が挙げられます。
グリーン建材とは、設計、施工、メンテナンス、改修の段階で建築構造の持続可能性と効率性を高めるような材料を指します。
グリーン建材として使用される材料には、竹・リサイクルプラスチック・ヘンプクリート(朝の屑と石灰の混合物)・ストローベイル(藁のブロック)・ティンバークリートなどがあります。
グリーン建材市場は2020年には全世界で2,990億ドルの規模に達しており、2026年まで年率9%で成長することが予測されています。
地域密着型のビジネス
建材卸売業は地域密着型のビジネスが特徴的です。
各地域ごとに建材卸売業者が存在しており全国展開する事業者が少ないため、寡占化が進行していない業界です。実際、主要10社の売上を合算しても業界全体の20%程度にとどまります。
各地域における同業者の競合社数は多くない一方、他業種との競争は激化しています。
近年では住設機器メーカーが新規実店舗の開設やオンラインショップなどでリフォーム需要を囲い込んでいるほか、エンドユーザーにあたる消費者に直接営業をかけることができる家電量販店が参入する事例もあります。
競争激化を背景として、建材卸売事業所数は業界全体の販売額と同様に1991年をピークに減少傾向にあります。
今後も価格競争は激しくなることが予想されるため、取り扱う建材を拡充する、自社で加工して流通させるといった戦略が求められます。
建材卸売業界のM&A動向
価格競争が激化している建材卸売業界では、取り扱う建材を拡充するM&Aや、サプライチェーンの上流・下流に位置する企業を垂直統合するためのM&Aが多く見られます。
前者のケースでは自社の取り扱っていない建材に強みを持つ他社を買収することで多様なニーズに対応することが可能になります。
後者の場合、建材メーカーを買収して仕入れから卸売までを自社内で完結させるほか、建設や工事業を営む企業を買収することで他社との差別化を図ることができます。
建材卸売業界におけるM&Aのメリット
売り手のメリット
建材卸売業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。
- 買い手の建材を取り扱えるようになる
- 買い手の顧客網を取り込むことが可能になる
- 取引先数を増加できため、価格交渉力が強くなる
- 後継者が不在の場合、廃業せず事業を継続し社員の雇用を守ることができる
- 後継者問題を解決し、株式譲渡による譲渡収入とともに経営から退くことができる
- M&Aを契機に代表者による借入金の個人保証や担保を解消できる

買い手のメリット
建材卸売業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。
- 売り手が取り扱う建材を新たに展開できる
- 新たな事業エリアに進出できる
- 仕入れ量の増加を通じてスケールメリットを享受できる
- 垂直統合の場合、リフォームやグリーン建材などの今後の需要拡大が見込める分野に進出できる
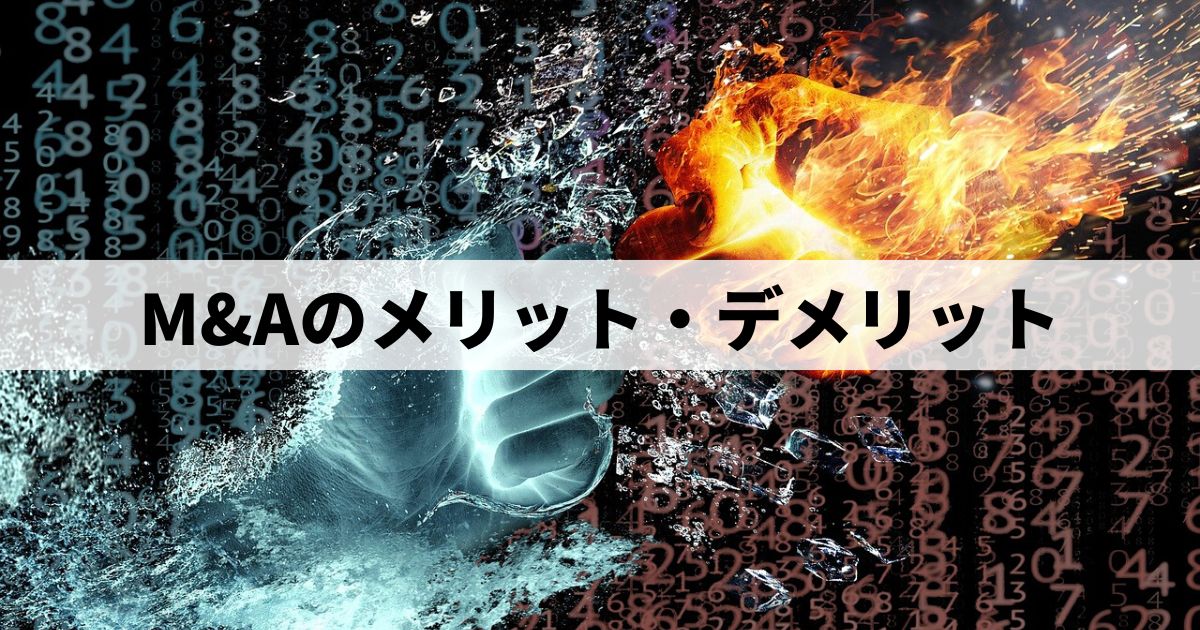
建材卸売業界のM&A・売却・買収事例
ブルケン東日本による建材販売事業・建築工事業のM&A
仙台市を拠点に建築資材販売事業を手掛けるブルケン東日本は、山形県寒河江市を中心に建築資材販売事業と建築工事業を手掛ける東洋住建から建材販売事業・建築工事業を譲り受けました。
- 実行時期:2022年4月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:東北地方への事業エリア拡大

アルコニックスによるソーデナガノのM&A
非鉄金属、レアメタル、レアアースなどの製品の販売、原材料の輸出入などを手掛けるアルコニックスは、リチウムイオン電池向けの金属部品の製造を手掛けるソーデナガノの株式を取得しました。
- 実行時期:2022年4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:88億3,700万円
- 目的:製造業と商社機能の融合
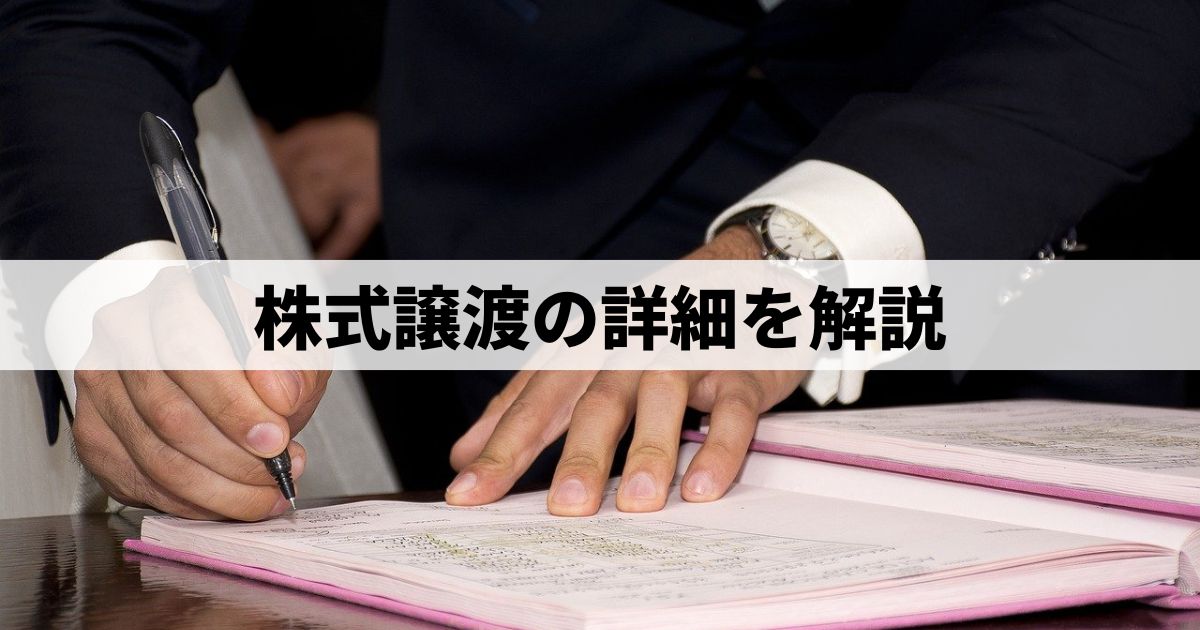
フクヤ建設による成商のM&A
注文住宅建築、リノベーション、オフィス・施設建築、宅地造成、不動産紹介などを手掛けるフクヤ建設は、鉄鋼建材卸売や建築金物加工事業を手掛ける成商の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業の多角化

ダイキアクシスによるアルミ工房萩尾のM&A
水回りを中心とする住宅設備機器卸売事業、水処理を中心とする環境機器の開発事業、再生可能エネルギー関連事業などを手掛けるダイキアクシスは、住宅サッシ・エクステリア建材の施工・販売業を手掛けるアルミ工房萩尾の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:商材の拡充・提案力強化

OCHIホールディングスによる寺田のM&A
西日本で建材・住宅設備機器卸売を中心に建材加工事業、環境アメニティ事業(空調・冷熱機器や家庭用品の販売)、各種建設工事業などを手掛ける企業グループの持株会社であるOCHIホールディングスは、寝具・衣料品・タオルなどの繊維商品の卸売事業を手掛ける寺田の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:東日本地域での事業拡大

コンドーテックによる栗山アルミのM&A
産業資材・鉄構資材の製造・仕入・販売、電設資材の仕入・販売を手掛けるコンドーテックは、非鉄金属の押出、アルミ押出型材などの製造開発、型材・板材・ステンレスなどの加工、アルミニュームの表面処理加工などを手掛ける栗山アルミの株式75.7%を取得しました。
- 実行時期:2021年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:アルミ商材の新規展開
東和アークスによる西武建材のM&A
建材の製造・卸売や再生可能エネルギー開発、石油燃料配達・サービスステーション運営などを手掛ける東和アークスは、西武ホールディングスの子会社で北関東・静岡を中心に建築材料と鉱物・金属材料を主とする製造・卸売業を手掛ける西武建材の全株式を取得しました。
- 実行時期:2021年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:事業ポートフォリオの拡大
JKホールディングスによるタムラの建築資材販売の事業のM&A
総合建材卸売事業を展開しているJKホールディングスは、木材・建材・住宅設備機器の販売施工等を行っているタムラより建築資材販売の事業を譲り受けました。
- 実行時期:2021年11月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:販売エリア拡大
JKホールディングスによる坂田建材のM&A
総合建材卸売事業を展開するJKホールディングスは、建材・鋼材・住宅機器の販売はなどを手掛ける坂田建材を子会社化しました。
- 実行時期:2021年3月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:岩手県内における拠点拡充と、東北地区におけるグループの経営基盤の強化
JKホールディングスによる京都板硝子のM&A
総合建材卸売事業を展開するJKホールディングスは、板硝子の卸売および工事業などを展開している京都板硝子を子会社化しました。
- 実行時期:2020年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:グループ事業の相乗効果創出とグループ全体の企業価値向上
岡部によるVimco Inc.の建材製品製造の事業のM&A
建設関連製品事業等を展開している岡部は、建材製品の製造・販売事業等を行っているVimco Inc.の建材製品製造の事業を譲り受けました。
- 実行時期: 2021年10月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:米国における年間売上高引き上げ
サンコーテクノによる新光ナイロンのM&A
建設資材などの企画開発や輸出入を行うサンコーテクノは、土木用暗渠排水材「ヘチマロン」等の製造・販売を行っている新光ナイロンを子会社化しました。
- 実行時期: 2023年4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:既存市場および新市場への販売拡大
飯田グループホールディングスによるオリエントのM&A
戸建分譲事業、マンション分譲事業などを展開している飯田グループホールディングスは、内装建材の製造販売を行っているオリエントを子会社化しました。
- 実行時期: 2021年01月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:住宅用内装建材の安定的調達によるコストシナジーの創出
阪和興業による三沢興産のM&A
鉄鋼を扱う総合商社の阪和興業は、特殊鋼および鋼材全般等の国内販売および輸出入業務を行う三沢興産と事業提携を行いました。
- 実行時期: 2023年03月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:住友電工グループとの製品販売面での協力関係強化
出光興産によるカナセキユニオンのM&A
燃料油や基礎化学品等の事業を行う出光興産は、石油・石油化学から資源のセグメントまで幅広く事業を展開しているカナセキユニオンを子会社化しました。
- 実行時期:2023年01月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:販路の効率化
日創プロニティによるワタナベテクノスのM&A
建築・建材、等の各種金属製品を提供している日創プロニティは、防音BOX・消音ダクト等の設計・製造・販売を行うワタナベテクノスを子会社化しました。
- 実行時期:2023年1月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:「加工力」の増強と、一貫生産体制の整備
北恵による古賀文化瓦工業所のM&A
新建材・住宅資材等の販売および施工付販売を行っている北恵は、屋根・壁を主に工事事業と販売事業を行う古賀文化瓦工業所を子会社化しました。
- 実行時期:2023年4月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:工事機能の融合による地域密着型の営業展開の強化
阪和興業による田中鉄鋼販売のM&A
鉄鋼を扱う総合商社である阪和興業は、一般鋼材販売および加工販売を行っている田中鉄鋼販売を子会社化しました。
- 実行時期:2022年12月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:サプライチェーンの再構築
日創プロニティによるニッタイ工業のM&A
建築・建材、等の各種金属製品を提供している日創プロニティは、タイル製造・販売を行っているニッタイ工業を子会社化しました。
- 実行時期:2022年08月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:幅広い市場対応による事業基盤の強化

綿半ホールディングスによる夢ハウスのM&A
グループ全体の経営戦略や新規事業企画などを行っている綿半ホールディングスは、プレカット材・建材製造販売事業等を行う夢ハウスを子会社化しました。
- 実行時期:2021年7月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:27億1,800万円
- 目的:グループの企業価値向上
太平洋セメントによるデンカのセメント販売事業会社のM&A
日本大手のセメントメーカーの太平洋セメントは、総合化学メーカーとしてセメント製造等を手掛けるデンカのセメント販売事業会社を譲り受けました。
- 実行時期:2023年3月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:デンカ青海工場で生産されたセメントの「太平洋セメント」のブランド名での販売
小野建による森田鋼材のM&A
鉄鋼・建材商社の小野建は、鉄筋コンクリート用異形棒鋼の加工から販売、施工まで提供している森田鋼材を子会社化しました。
- 実行時期:2019年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:関西における取扱量の拡大による地場密着型ビジネスの展開
佐田建設による前橋機材センターのM&A
建設工事の受注・施工等を行っている佐田建設は、建設用資機材機器・機械装置の賃貸および販売などを手掛ける前橋機材センターを吸収合併しました。
- 実行時期:2023年4月
- スキーム:吸収合併
- 取引価額:非公開
- 目的:経営資源集約と効率的な組織運営
小野建によるヤマサのM&A
鋼材や金物・土木建築材料専門の商社である小野建は、鉄鋼・土木建築資材の販売、工事請負事業を行っているヤマサを子会社化しました。
- 実行時期:2022年11月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:高知県における物流拠点化を通じた顧客へのサービス向上
グッドニュースによるサンワカンパニーのM&A
専門職・技術職に特化したプラットフォーム「CareerMap」を運営するグッドニュースは、住宅設備機器・建築資材販売等を行うサンワカンパニーと資本業務提携を行いました。
- 実行時期:2022年8月
- スキーム:資本業務提携
- 取引価額:非公開
- 目的:人手不足の解消
ヤマダHDによるナイスのM&A
グループ経営戦略の企画やグループ共通業務などを行っているヤマダHDは、建築資材事業、住宅事業、木造建設事業、等を展開するナイスを子会社化しました。
- 実行時期:2021年8月
- スキーム:第三者割当増資
- 取引価額:39億2,000万円
- 目的:相互の競争力および取引の強化・拡充による企業価値の向上
日本興業による新茨中のコンクリート二次製品製造・販売事業のM&A
建設用コンクリート製品製造や建設工事等を行っている日本興業は、コンクリート二次製品等の事業を行う新茨中のコンクリート二次製品製造・販売事業を譲り受けました。
- 実行時期:2022年4月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:東日本地区の生産拠点を確保による効率的な事業運営拡充
伊藤忠商事によるLouisiana Pacificの住宅用構造材製造事業のM&A
大手総合商社の伊藤忠商事は、建材メーカーであるLouisiana Pacific住宅用構造材製造事業を取得しました。
- 実行時期:2022年8月
- スキーム:事業譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:米国2工場、カナダ1工場の取得
JFE商事によるCalifornia Expanded Metal Products Co.のM&A
鉄鋼製品や鉄鋼原料等の国内外間取引を行うJFE商事は、建築向け構造用・内装用鋼製フレーム等の製造・販売を行っているCalifornia Expanded Metal Products Co.を子会社化しました。
- 実行時期:2022年08月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:米国の薄板建材分野へ本格参入による事業拡大
伊藤忠丸紅鉄鋼による英国Barclay&Mathieson LimitedのM&A
鉄鋼専門商社である伊藤忠丸紅鉄鋼は、少量多品種の建材製品の加工・販売を行っている英国Barclay&Mathieson Limitedを子会社化しました。
- 実行時期:2022年10月
- スキーム:株式譲渡
- 取引価額:非公開
- 目的:英国における地位構築と、欧州グループにおける事業領域の拡大
おわりに
本記事のまとめ
建材卸売業界の市場動向、M&A動向、買収事例についてご紹介しました。
建材卸売業界は、納入先となる建設業の動向に左右されます。現在は新規住宅需要が低下してきているため、これに連動して建材の需要も減少傾向にあります。
今後はリフォーム需要に対応した建材や、環境に配慮したグリーン建材など提案できる建材のラインナップを拡充することを目的としたM&Aが加速すると見込まれます。

M&A・事業承継のご相談はハイディールパートナーズへ
M&A・事業承継のご相談は経験豊富なM&Aアドバイザーの在籍するハイディールパートナーズにご相談ください。
ハイディールパートナーズは、中堅・中小企業様のM&Aをご支援しております。弊社は成約するまで完全無料の「譲渡企業様完全成功報酬型」の手数料体系を採用しており、一切の初期費用なくご活用いただけます。
今すぐに譲渡のニーズがない企業様でも、以下のようなご相談を承っております。
- まずは現状の自社の適正な株式価値を教えてほしい
- 株式価値を高めるために今後何をすればよいか教えてほしい
- 数年後に向けて株式価値を高める支援をしてほしい
- どのような譲渡先が候補になり得るか、業界環境を教えてほしい
ご相談は完全無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。


