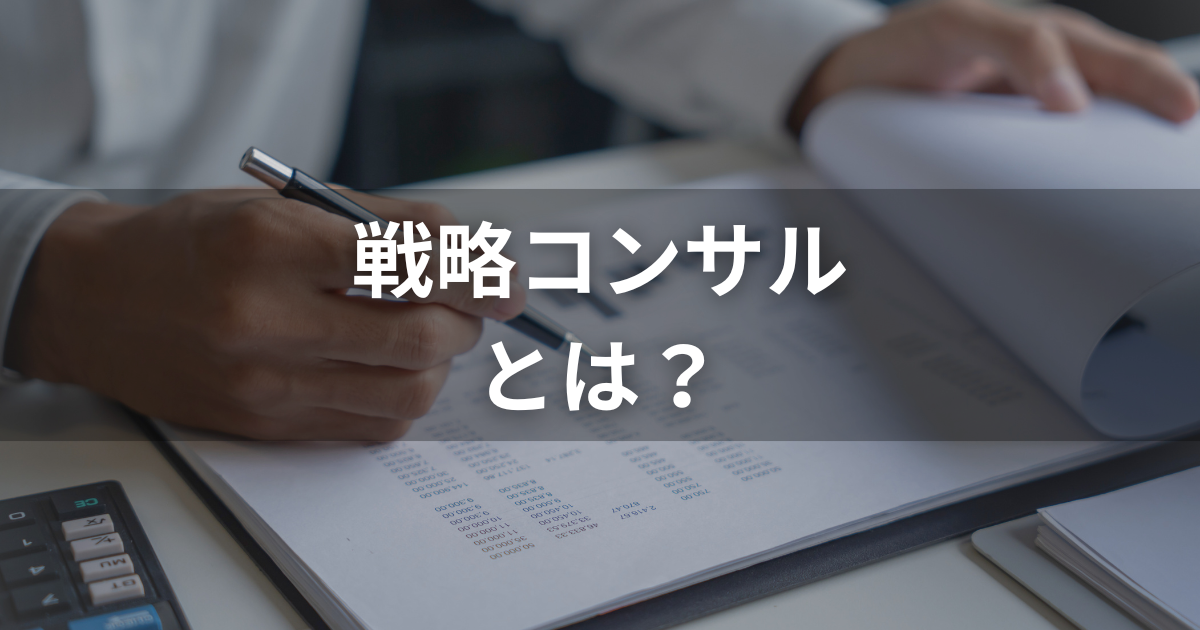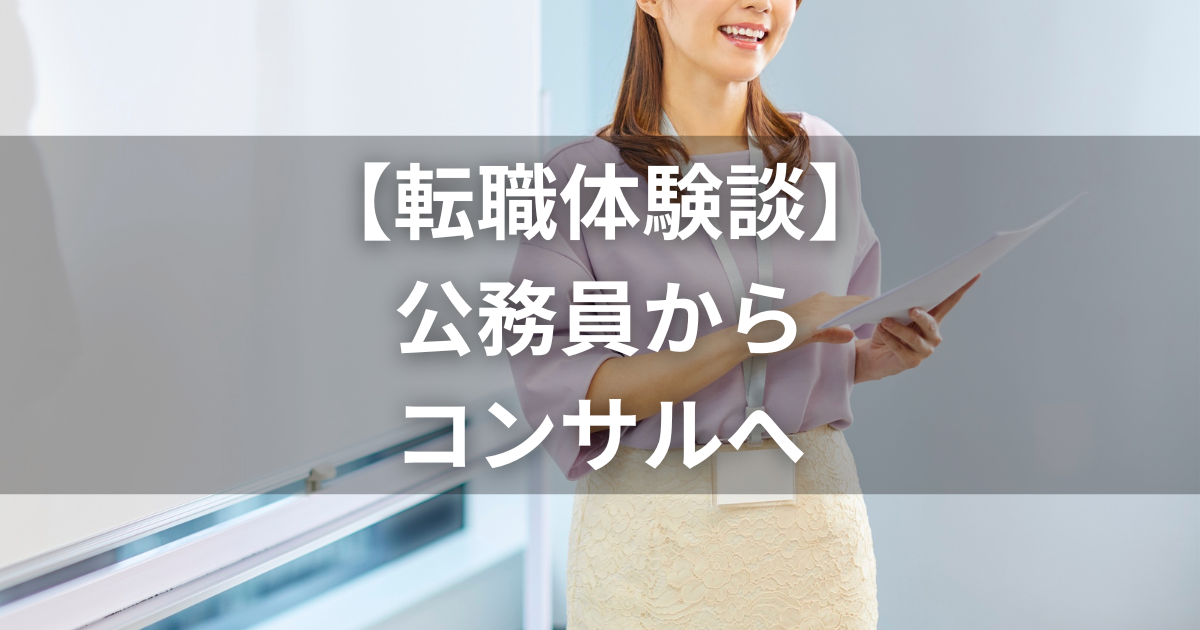【転職体験談】自動車メーカーの研究開発職から日系戦略コンサルへ
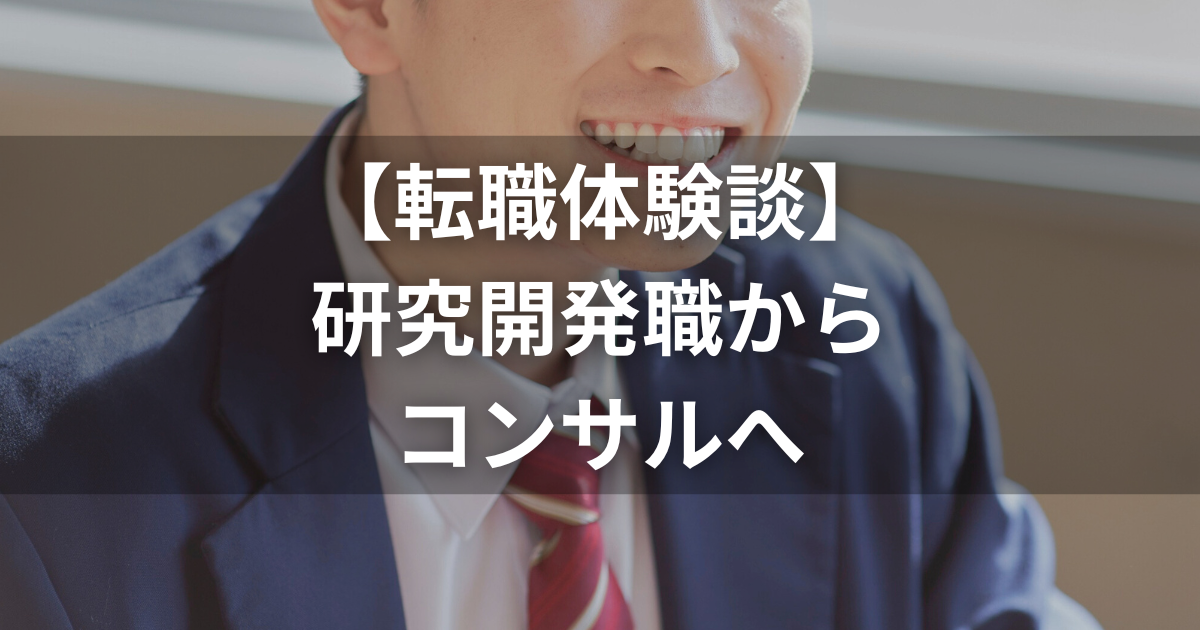
Mさんは、有名国立大学大学院の工学系研究科を卒業後、日系大手自動車メーカーで研究開発職として約7年間勤務。自動運転技術や電動化システムの開発に携わる中で、技術の社会実装における経営戦略の重要性を実感。2024年に日系戦略コンサルティング会社へ転職し、製造業クライアントの事業戦略立案を中心に活躍中。
- お名前:Mさん(男性) ※仮名
- 年齢:31歳
- 学歴:国立大学大学院卒(工学系研究科)
- 職歴:日系自動車メーカー(研究開発)→日系戦略コンサル(シニアアソシエイト)
転職前のキャリアと葛藤
現職までのご経歴を教えていただけますか
大学院では機械学習を活用した制御システムの研究をしていました。当時はまだAIブームの前でしたけど、自動運転への応用可能性には魅力を感じていたんです。就活では、研究を直接活かせる自動車メーカーの研究開発職を選びました。
入社してから約7年間、主に自動運転技術の要素開発と、電動化システムの研究に従事していました。最初の3年間は基礎研究チームで、センサーフュージョン技術の開発を担当。その後、量産化プロジェクトに異動して、実際の車両への実装を経験しました。
技術的にはすごく面白い仕事でした。特許も出願できましたし、国際学会での発表機会もありました。ただ、徐々に「この技術、本当に世の中に出るのかな?」という疑問を持つようになったんです。技術的には完成度が高くても、事業判断で日の目を見ないプロジェクトを何度も目にして…。
学生時代の研究と実務のギャップはありましたか?
ぶっちゃけ、ギャップだらけでしたよ(笑)。大学院では「技術的に優れていれば評価される」世界でしたけど、企業では「コスト」「量産性」「市場性」という現実的な壁がありました。
例えば、認識精度を1%上げるために開発費を1億円かけるか?という判断。研究者としては「精度向上は絶対正義」と思いがちですが、経営的には「その1%に1億円の価値があるか」を考えなきゃいけない。この視点の違いに、最初はかなり戸惑いました。
でも、この経験が今のコンサル業務では武器になっています。技術の本質的な価値と、ビジネス的な制約の両方を理解できるのは強みだと感じていますね。
転職を考えはじめたきっかけや理由を教えてください
直接的なきっかけは、2023年の春に参加した経営戦略会議でした。私たちが2年かけて開発した技術の事業化判断の場だったんですが、結果は「投資凍結」。技術的には世界トップレベルだったのに、市場環境や投資回収の観点から見送りになったんです。
正直、めちゃくちゃ悔しかったです。でも同時に「経営判断の重要性」を痛感しました。どんなに優れた技術も、適切な事業戦略がなければ社会実装されない。むしろ、技術がわかる人間こそ、経営戦略の立案に関わるべきじゃないかって。30歳を目前にして、「このまま同じ環境で40歳、50歳を迎えていいのか」という焦りもありましたね。
ご家族の反応はいかがでしたか?
実は妻の方が積極的でした。「やりたいことがあるなら、チャレンジした方がいい」って背中を押してくれました。ただ、住宅ローンを組んだばかりだったので、年収が下がることへの不安は正直ありました。
自分の両親は最初反対でしたね。「せっかく大手企業に入ったのに」「研究職は安定してるじゃないか」って。特に父親は同じメーカー出身だったので、気持ちは分かるんですけど…。でも、自分のキャリアビジョンを具体的に説明したら、最終的には「お前の人生だから」と理解してくれました。
転職活動の実際
転職活動を進める中で苦労したのはどのような点ですか
一番苦労したのは、「なぜコンサル?」という質問への回答でした。エンジニアからコンサルって、キャリアチェンジとしては結構大きいじゃないですか。面接官も「技術を捨てることになるけど、本当にいいの?」という視点で見てくる。
最初は「経営戦略に興味がある」とか抽象的な回答しかできなくて、ことごとく落ちました。戦略系ファームを5社受けて、書類は通っても面接で全滅。特にケース面接は本当に難しかった。エンジニアって「正解」を求めがちですけど、コンサルの場合は「最適解」を短時間で導き出す必要がある。この思考の切り替えに苦戦しました。
エージェントからはどのような支援を受けましたか?
エージェントは3社使いました。正直、当たり外れが大きかったです。1社目は大手でしたけど、担当者が若くて業界知識が浅く、一般的なアドバイスしかもらえませんでした。
2社目で出会った担当者が元コンサルタントで、この人が転機になりました。履歴書の書き方から、各ファームの特徴、面接官の傾向まで、具体的なアドバイスをくれました。特に「技術バックグラウンドを強みとして、どう差別化するか」という戦略を一緒に考えてくれたのが大きかったです。
例えば、「AIの技術的限界を理解している」ことを、「クライアントに現実的な提案ができる」という価値に変換する、といった具体的な伝え方を教えてもらいました。また、年収交渉も代行してくれて、最初の提示から50万円アップできました。エージェント選びは本当に重要だと実感しましたね。
エージェントとのやり取りで印象的だったエピソードはありますか?
ある面接で失敗した後、担当エージェントが2時間も電話で振り返りをしてくれたんです。夜の11時過ぎでしたけど、「Mさんの強みが伝わってない。もっと具体例を使いましょう」って。
その時に言われたのが、「エンジニアの謙虚さは美徳だけど、コンサル転職では自己PRが命」ということ。確かに私、実績を控えめに話す癖があったんです。ここから、きちんとこれまでの成果を定量的に面接内で訴求していくことを心掛けました。
新天地での挑戦
今の会社を選んだ決め手はなんでしたか
最終的に2社から内定をもらいました。1社は外資系の戦略ファーム、もう1社が今の日系ファームです。正直、ブランド力や年収は外資系の方が上でした。提示年収で150万円くらいの差がありましたし。
でも、最終的に日系を選んだのは「クライアントとの距離感」と「技術への理解」です。面接で会った日系ファームのパートナーが元メーカーの技術者で、「技術がわかるコンサルタントの価値」を熱く語ってくれたんです。「日本の製造業を真の意味で支援できるのは、技術を理解している我々だ」と。
あと、プロジェクトの期間も決め手でした。外資系は3ヶ月程度の短期プロジェクトが中心でしたが、日系は半年から1年の長期案件が多い。クライアントと深い関係を築いて、実装まで支援できる点に魅力を感じました。「提案して終わり」じゃなくて、「一緒に実現する」スタンスが、エンジニア出身の私には合っていると思ったんです。
実際に入社してみて、イメージとのギャップはありましたか?
良い意味でのギャップが大きかったです。「コンサルは激務」というイメージでしたが、実際は前職の方が残業時間は多かったくらい。もちろん、プロジェクトによって波はありますけど、平均すると月60時間程度の残業です。前職は80時間超えも珍しくなかったので。
ただ、仕事の密度は段違いに濃いです。1時間のミーティングでも、事前準備に3時間かけるのが普通。クライアントの期待値も高いので、常に120%の成果を求められます。でも、この緊張感が心地良いんです。毎日が勝負というか、成長を実感できるというか。
意外だったのは、チームワークの重要性です。コンサルって個人プレーのイメージでしたけど、実際はチーム戦。特に私みたいな未経験者は、先輩のサポートなしには仕事になりません。入社3ヶ月は、マネージャーが毎日1時間、個別指導してくれました。
今の会社に入ってよかったこと、苦労していることを教えてください
一番良かったのは、視座が格段に上がったことです。前職では「技術をどう実装するか」を考えていましたが、今は「この技術投資は企業価値向上にどう貢献するか」を考えています。同じ技術でも、見る角度が180度変わりました。
具体例を挙げると、最近担当した製造業のDXプロジェクト。クライアントは「AIを導入したい」と言っていましたが、我々の分析では「まずは業務プロセスの標準化が先」という結論に。技術導入ありきじゃなくて、本当に必要な改革を提案できたのは、技術の限界を知っているからこそだと思います。結果的に、初年度で2億円のコスト削減を実現できました。
苦労している点は、やはり知識のキャッチアップです。財務分析、M&A、組織論など、学ぶべきことが山積み。週末も勉強していますし、通勤時間はビジネス書を読んでいます。あと、クライアントマネジメントも難しい。技術者相手なら専門用語で話せますけど、経営層には別の言語で話さないといけない。この「翻訳力」を身につけるのに苦労しています。
年収や待遇面での変化はいかがですか?
ぶっちゃけ、入り口の年収は前職から100万円ほど上がりました。早ければ来年にはマネージャー昇進の可能性があるので、更なる高年収も見えてきてます。現職のマネージャーの年収は前職だと40歳過ぎにならないともらえないような金額なので、キャリアアップは加速しましたね。
ただ、お金以上に価値があるのは「市場価値の向上」です。転職活動を始めた時は、コンサル以外の選択肢がほぼありませんでした。でも今は、事業会社の経営企画や、ベンチャーのCxOポジションからスカウトが来ます。選択肢が広がったことが、精神的な余裕につながっています。
福利厚生は前職の方が充実していました。社宅もないし、企業年金も少ない。でも、その分を自己投資に回せているので、長期的にはプラスだと考えています。
転職を成功させるポイント
転職活動を振り返って、成功のポイントは何だったと思いますか?
3つあると思います。1つ目は「差別化ポイントの明確化」。エンジニアからコンサルという転職は珍しくないですけど、「技術の限界を知っているからこそ、現実的な戦略を立案できる」という価値提案は評価されました。
2つ目は「準備の徹底」。4ヶ月で数百時間は対策に使ったと思います。特にケース面接は、量をこなさないと上達しない。模擬面接の録音を聞き返して、改善点をノートにまとめる作業を繰り返しました。
3つ目は「タイミング」です。30歳という年齢は、未経験転職のラストチャンスだと思っていました。35歳を超えると、即戦力が求められる。若さという武器があるうちに動いて正解でした。

もし転職前の自分にアドバイスするなら、何と言いますか?
「もっと早く動け」ですね(笑)。27、28歳で転職していれば、今頃はもっと上のポジションにいたかもしれない。でも、技術者としての経験を積んだからこそ、今の強みがあるとも思うので、難しいところですけど。
あと、「社外のネットワークを作っておけ」とも言いたいです。転職活動を始めてから人脈作りをしても遅い。普段から勉強会や交流会に参加して、他業界の人と話す機会を作っておくべきでした。
それから、「英語はやっておけ」。コンサルでは英語の資料を読む機会が多いですし、グローバルプロジェクトもあります。TOEIC800点はあった方がいい。私は入社してから慌てて勉強し直しています。
同じようにエンジニアから転職を考えている人へのメッセージをお願いします
エンジニアの経験は、思っている以上に他業界で評価されます。論理的思考力、数字への強さ、プロジェクトマネジメント経験。これらは全て転用可能なスキルです。
ただし、「技術が好き」という理由だけでエンジニアをやっているなら、転職はおすすめしません。私の場合、「技術を使って世の中を変えたい」という思いがあったから、コンサルという手段を選びました。手段が変わっても、目的が明確なら、きっとうまくいきます。
転職は確かにリスクです。でも、「現状維持もリスク」だと思うんです。特に今の時代、一つの会社で定年まで働く保証なんてない。だったら、自分の市場価値を高める選択をした方がいい。失敗しても、その経験は必ず次に活きますから。
今後のキャリア展望
今後のキャリア展望を教えてください
短期的には、まずマネージャーを目指します。今は先輩について学んでいる段階ですが、来年には自分でプロジェクトを回せるようになりたい。特に、製造業のDXや、技術経営戦略の領域で専門性を確立したいです。
中期的には、35歳までにシニアマネージャー、40歳でパートナーというのが目標です。かなりチャレンジングですけど、不可能じゃないと思っています。技術バックグラウンドを活かして、「製造業に最も詳しいコンサルタント」というポジションを確立したいんです。
長期的には、事業会社に戻る選択肢も考えています。CTO兼経営企画のような、技術と経営の橋渡し役として。または、技術系スタートアップの経営に参画するのも面白いかもしれません。コンサルで培った経営視点と、エンジニア時代の技術力を融合させて、イノベーションを起こしたいです。
具体的にどんなスキルを身につけたいですか?
今、最も強化したいのは「ストーリーテリング力」です。データや分析は得意ですけど、それを魅力的な物語として伝える力がまだ弱い。クライアントの心を動かすプレゼンテーションができるようになりたいです。
あとは、ファイナンス知識の深化です。M&Aや企業価値評価など、より専門的な領域にも踏み込みたい。最近、中小企業診断士の勉強も始めました。資格自体が目的じゃなくて、体系的な経営知識を身につけるためです。
技術面では、AIやデータサイエンスの最新動向は追い続けています。月に1本は論文を読んで、技術トレンドを把握。コンサルタントとしての差別化要因は、やはり技術への深い理解だと思うので。
最後に、読者へのメッセージをお願いします
転職って、人生の大きな決断です。私も散々悩みました。でも、悩んでいる時間があったら、まず一歩踏み出してみることをおすすめします。転職活動をしたからって、必ず転職しなきゃいけないわけじゃない。
活動を通じて、自分の市場価値がわかります。何が強みで、何が足りないのか。その気づきだけでも、価値があると思います。私も最初の面接で惨敗して、自分の実力不足を痛感しました。でも、それがあったから必死に勉強したし、成長できました。
「今の環境に不満がある」「もっと成長したい」と思っているなら、動いてみてください。失敗しても、それは経験という財産になります。成功すれば、新しい世界が広がります。どちらに転んでも、現状維持よりは確実に前進できます。
最後に、家族の理解と支援は本当に大切です。私は妻の支えがなければ、転職なんてできませんでした。転職は個人の決断ですけど、影響は家族にも及びます。しっかり話し合って、一緒に未来を描くことが成功の秘訣だと思います。皆さんの挑戦を、心から応援しています!