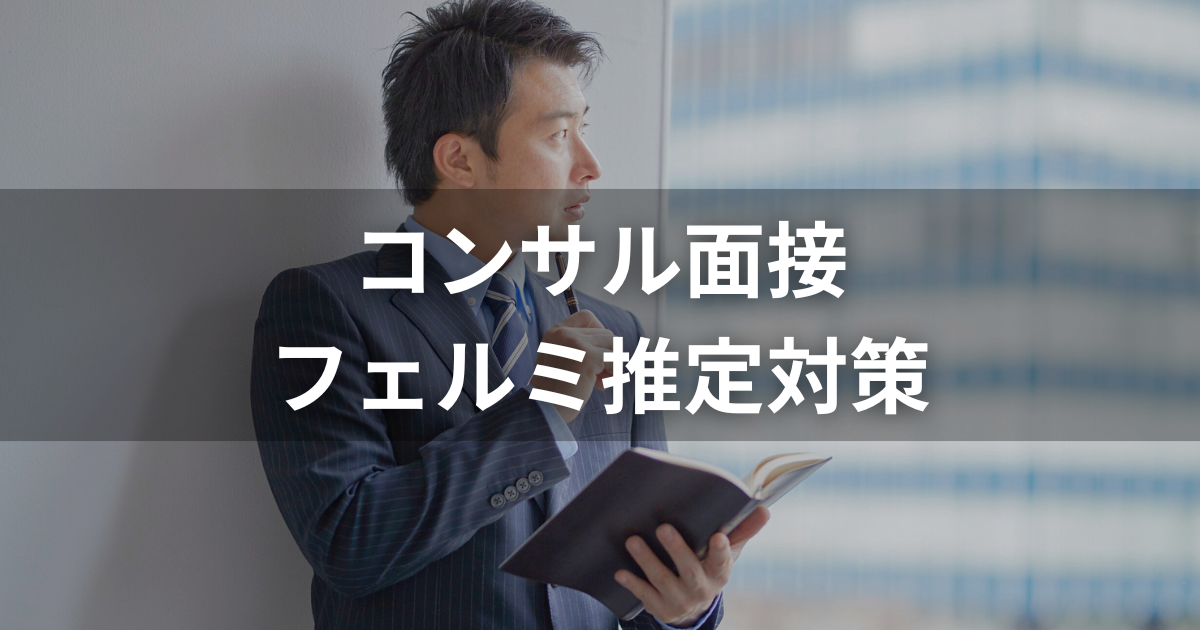フェルミ推定とは?くだらないと言われる理由と面接で問われる本当の価値
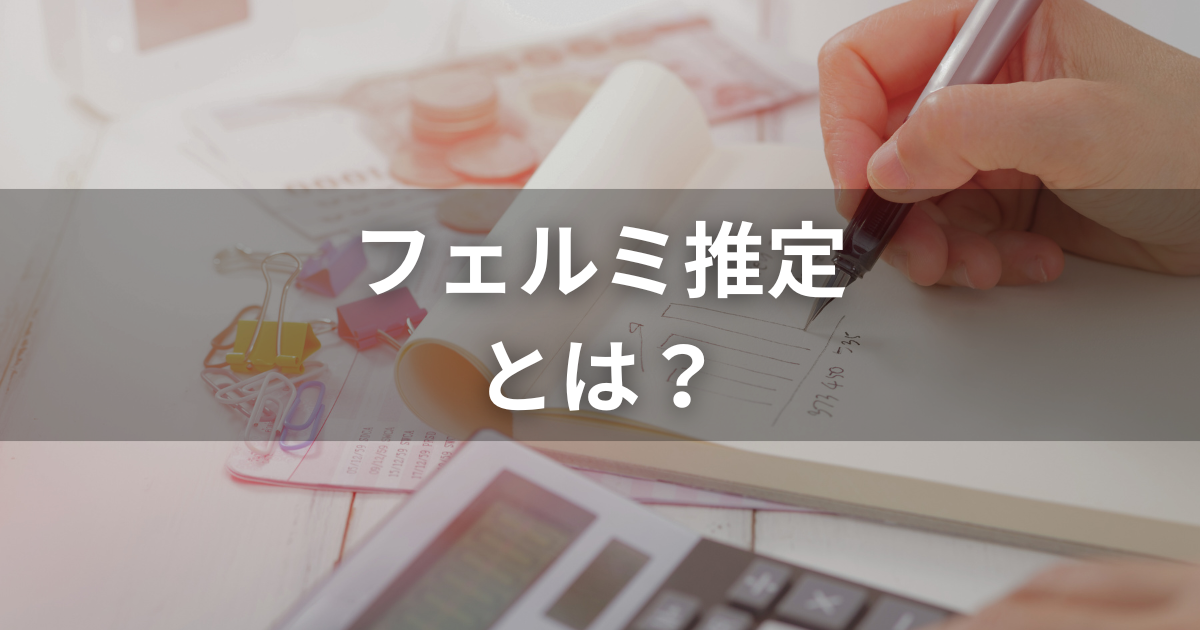
「日本の電柱の数は?」「コンビニの1日の売上は?」―こんな突飛な質問を面接で聞かれたらどう答えますか?これがフェルミ推定です。一見くだらないと思われがちですが、コンサルや総合商社の面接では今も重視される選考手法です。
本記事では、フェルミ推定への懐疑心を認めた上で、なぜ企業が重視するのか、どう対策すれば効率的か、実務でどう活きるのかを明確に解説します。読了後には、面接への不安が解消され、自信を持って臨める状態になることをお約束します。解法の型、必須の基礎知識、頻出パターンまで、あなたの疑問に全て答えます。
なぜフェルミ推定は「くだらない」と言われるのか?4つの理由と反論
Google採用廃止の真相:日本企業が続ける理由
フェルミ推定への懐疑心を語る上で避けて通れないのが、Googleが2013年に採用を廃止した事実です。同社の人事責任者は「業務パフォーマンスとの相関がない」と結論付けました。
しかし日本のコンサル・商社では依然として重視されています。この差は、日本企業が重視する「構造的思考力」と「プレッシャー下での対応力」を測る手段として、フェルミ推定が有効だと考えているためです。
参考:「地頭力」試すのは時間の無駄だった グーグル人事責任者、衝撃の告白: J-CAST 会社ウォッチ
「答えの誤差が大きすぎる」問題:評価されるのは精度ではない
「日本の電柱の数は?」という問いに対し、実際の答えと推定値が桁違いに異なることは珍しくありません。しかし企業が評価するのは数値の正確性ではなく、問題を論理的に分解し、妥当な仮説を立てる思考プロセスです。
面接官は「なぜその前提を置いたのか」「どのような構造で考えたか」を重視し、候補者の論理的思考力を見極めています。
パターン暗記化への批判:型の習得と思考力の関係
フェルミ推定対策が「解法パターンの暗記」に陥っているという批判は確かに存在します。人口ベース、面積ベース、需要ベースなど、定番の分解パターンを覚えるだけでは本質的な思考力は身につきません。
しかし、基本的な「型」を習得することは、複雑な問題に対処する際の土台となります。スポーツの基本フォームと同様、型の習得から応用への発展が重要なのです。
実務での使用頻度:データ時代におけるフェルミ推定の位置づけ
確かに実務では正確なデータや市場調査レポートを使うことが一般的です。しかし新規事業の初期検討、データが存在しない新市場の規模推定、仮説構築の場面では、フェルミ推定的な思考が活用されます。
完璧なデータがない状況で素早く概算し、意思決定の材料とする能力は、変化の速いビジネス環境において依然として価値があります。
フェルミ推定の本質:企業が本当に評価する3つの能力
論理的思考力:複雑な問題を構造化する力
フェルミ推定で最も評価される能力は、曖昧で複雑な問題を論理的に分解し、構造化する力です。「日本のマンホールの数」という漠然とした問いを、都市部と地方、道路の種類、設置密度などの要素に分解し、MECEに整理する過程で論理的思考力が試されます。
この能力は、実際のコンサルティング業務での課題解決アプローチと直結しています。
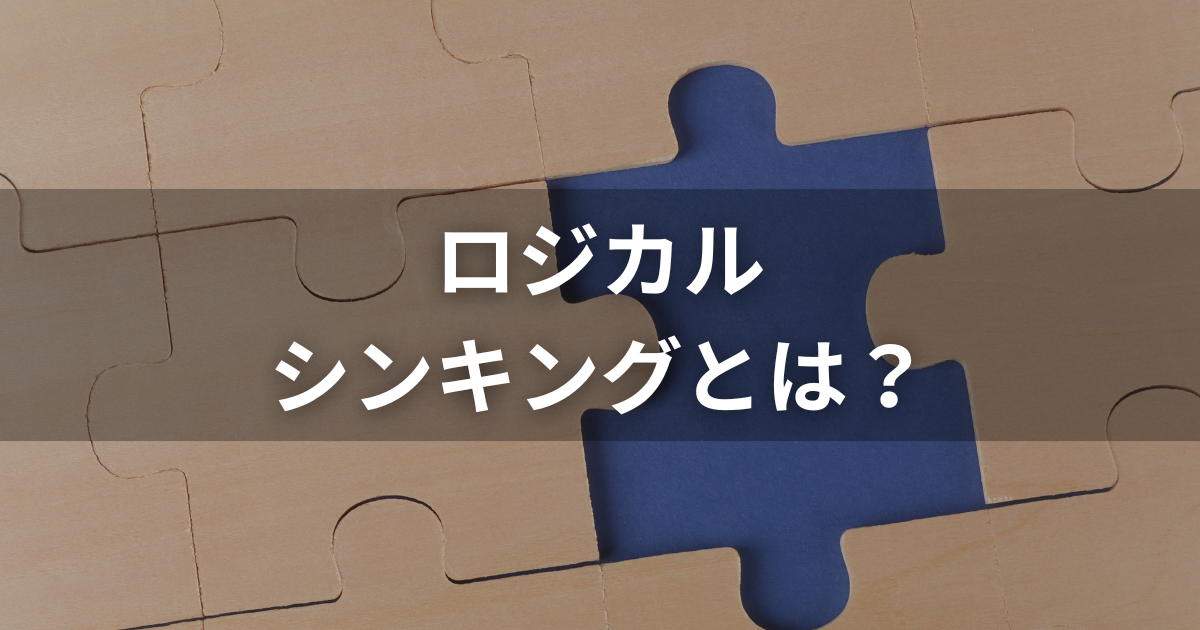
仮説構築力:不確実性の中で判断する力
ビジネスの現場では、完全な情報が揃うことはほとんどありません。フェルミ推定は、限られた情報から妥当な仮説を立て、それを根拠に推論を進める能力を測ります。
例えば「コンビニの1日の売上」を推定する際、客単価や来店頻度について合理的な仮説を設定し、その妥当性を説明できるかが重要になります。
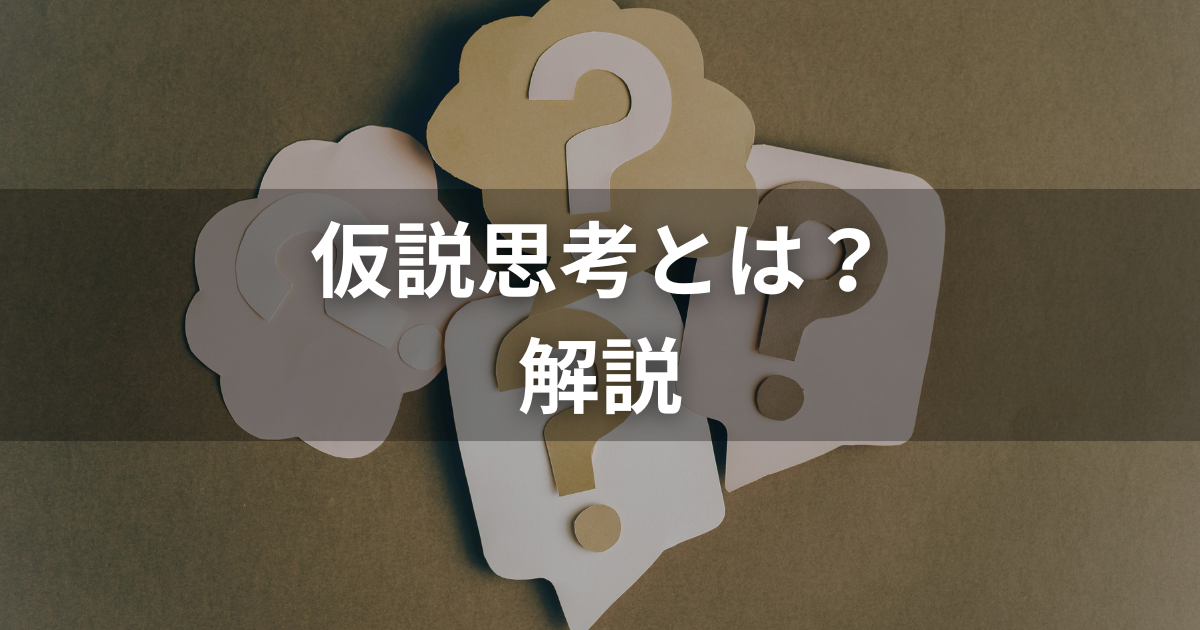
コミュニケーション力:思考を明確に伝える力
フェルミ推定の面接では、単に答えを出すだけでなく、思考プロセスを面接官に明確に伝える力が評価されます。前提条件の共有、計算過程の説明、結果の妥当性チェックなど、相手を巻き込みながら議論を進める能力は、実際のクライアントワークでも不可欠です。
対話的なやり取りを通じて、コミュニケーション力が試されているのです。
最短で身につく!フェルミ推定の解法4ステップ
問題定義と前提確認(What)
フェルミ推定の第一歩は、問題文を正確に理解し、定義を明確化することです。「日本の電柱の数」であれば、電柱の定義(電力用か通信用か)、対象地域(離島を含むか)などを確認します。
都市部と地方で設置密度が異なることを考慮し、それぞれの特性を整理します。この段階で前提条件を面接官と共有することが、後の議論をスムーズに進める鍵となります。
構造分解とアプローチ設計(How)
問題を論理的に分解し、計算可能な要素に落とし込みます。トップダウン型(全体から部分へ)とボトムアップ型(部分から全体へ)のアプローチを使い分けることが重要です。
人口ベース、面積ベース、需要ベースなど、問題に応じて最適な分解方法を選択します。MECEな分解を心がけ、抜け漏れや重複がないよう構造を設計します。
数値設定と計算実行(Which)
構造分解で特定した各要素に、妥当な数値を設定します。日本の人口1.25億人、世帯数5500万など、基本的な統計データは事前に暗記しておくことが推奨されます。
計算では概算テクニックを活用し、3.14を3に、365日を400日に置き換えるなど、精度と速度のバランスを取ります。暗算が困難な場合は、桁数の確認を優先します。
検証と結論導出(So What)
計算結果の妥当性を検証し、別のアプローチでクロスチェックを行います。極端に大きい・小さい数値が出た場合は、前提や計算過程を見直します。
最終的な結論では、単に数値を述べるだけでなく、その意味や示唆を付け加えます。面接では時間配分も重要で、各ステップに適切な時間を割り当て、詰まった際のリカバリー方法も準備しておく必要があります。
必須の基礎知識:これだけは覚えておくべき数値データ
人口・世帯関連データ
フェルミ推定で最も頻出する基礎データは人口関連の数値です。日本の総人口約1.25億人、世帯数約5500万、平均世帯人数2.3人は必須の暗記項目です。
年齢構成では、65歳以上が約30%、生産年齢人口が約60%という概数も押さえておきましょう。東京都の人口1400万人、大阪府880万人など、主要都市の人口も面接で活用できます。
参考:統計局ホームページ/人口推計/人口推計、日本の世帯数の将来推計(全国推計)、日本の世帯数の将来推計(全国推計)、東京都の人口(推計)、大阪府の毎月推計人口
地理・経済関連データ
日本の国土面積38万平方キロメートル、GDP約550兆円は基本中の基本です。主要産業の市場規模として、自動車産業60兆円、建設業50兆円、小売業150兆円などを把握しておくと、ビジネス系の推定で役立ちます。
コンビニ店舗数5.5万店、ガソリンスタンド3万店など、身近な施設の概数も面接でよく使われます。
参考:令和7年7月1日時点の全国都道府県市区町村別面積を公表 ~能登半島地震による面積変動を反映~ | 国土地理院、500兆円を超えてから32年…日本の名目GDPようやく600兆円超え、報道発表資料:令和7年度(2025年度)建設投資見通し、2024年小売業販売を振り返る|その他の研究・分析レポート、令和6年度末揮発油販売業者数及び給油所数を取りまとめました
計算を簡単にする概算テクニック
フェルミ推定では、正確な計算より素早い概算が重要です。円周率3.14は3に、1年365日は400日に置き換えることで、暗算が容易になります。
また、「約」を効果的に使い、1234万を1200万と丸めるなど、有効数字を2桁程度に留めます。掛け算では、大きな数を10の累乗に分解し、5×8=40のような基本的な計算に帰着させるテクニックも有効です。
実践演習:頻出パターン別の例題と解答プロセス
「数」を問う問題
日本の電柱の数
「日本の電柱の数」を推定する際は、面積ベースと人口ベースの両方のアプローチを検討し、より妥当と思われる方法を選択します。面積ベースでは、日本の国土を都市部と地方に分け、それぞれの設置密度を仮定します。
都市部(全国土の10%=3.8万km²)では100m間隔で設置されると仮定すると、1km²あたり100本。地方(90%=34.2万km²)では500m間隔で1km²あたり4本。計算式:都市部3.8万km²×100本+地方34.2万km²×4本=380万本+137万本=約520万本。
一方、人口ベースでは世帯数5500万×0.8(電柱がある地域の割合)×道路に面する割合0.5=2200万本。両者の平均を取って約1400万本と推定します。
日本のマンホールの数
「日本のマンホールの数」では、道路延長をベースに考えます。
日本の道路総延長は約120万km。マンホールは下水道、電気、ガス、通信など複数の用途があります。下水道用が最も多く、市街地では50m間隔、郊外では200m間隔で設置と仮定。
市街地の道路40万km÷0.05km×2(両側)=1600万個、郊外80万km÷0.2km×1=400万個。その他インフラ用を含め合計約2500万個と推定。
このように要素を分解し、それぞれに妥当な数値を設定することが重要です。
日本のコンビニ店舗数
「日本のコンビニ店舗数」は、人口ベースで推定します。日本の人口1.25億人を、コンビニ1店舗あたりの商圏人口で割ります。
都市部では2000人に1店舗、地方では4000人に1店舗と仮定。都市部人口8000万人÷2000人=4万店、地方4500万人÷4000人=約1.1万店、合計5.1万店。実際の店舗数約5.5万店に近い数値となり、推定の妥当性が確認できます。
複数の角度から検証することで、より説得力のある回答となります。
「市場規模」を問う問題
日本の缶コーヒー市場規模
「日本の缶コーヒー市場規模」を需要側から推定します。
成人人口1億人のうち、缶コーヒー飲用者を60%(6000万人)と設定。飲用者を3セグメントに分類:ヘビーユーザー(20%、毎日2本)、ミドルユーザー(40%、週3本)、ライトユーザー(40%、週1本)。年間消費量はヘビー:1200万人×2本×365日=88億本、ミドル:2400万人×3本×52週=37億本、ライト:2400万人×1本×52週=12億本。
合計137億本×平均単価120円=約1.6兆円。季節変動(夏場1.3倍)を考慮した補正後も同程度の規模と推定されます。
日本のラーメン店市場規模
「日本のラーメン店市場規模」は店舗数×平均売上で算出します。
全国のラーメン店を3万店と仮定(個人店2万店、チェーン店1万店)。個人店の1日売上:客数60人×客単価1000円=6万円、年間6万円×300日営業=1800万円。チェーン店:客数150人×客単価900円=13.5万円、年間13.5万円×350日=約4700万円。
市場規模:個人店2万店×1800万円+チェーン店1万店×4700万円=3600億円+4700億円=約8300億円。カップ麺や冷凍ラーメンは含まない外食市場のみの推定値です。
日本の映画市場規模
「日本の映画市場規模」は興行収入から推定します。
年間のべ観客数を算出:日本人口1.25億人×年間平均鑑賞回数1.5回=約1.9億人。チケット価格を平均1400円(一般1900円とシニア・学生割引の加重平均)とすると、1.9億人×1400円=約2660億円。これにポップコーンなどの売店収入(観客の50%が平均500円購入):1.9億人×0.5×500円=約475億円を加えると、劇場関連の市場規模は約3100億円。
配信やDVDを含めた映画産業全体では、この2倍程度の約6000億円規模と推定されます。
「売上」を問う問題:特定店舗・企業の売上推定
駅前コンビニの1日の売上
「駅前コンビニの1日の売上」を時間帯別に詳細に分解して推定します。まず立地条件を整理:主要駅の改札から徒歩1分、オフィスビル密集地域、競合店舗が半径200m以内に2店舗存在。営業時間は24時間、売場面積は標準的な150㎡と仮定。時間帯を4つに分け、それぞれの客層、来店者数、購買行動を分析します。
朝の時間帯(6-10時)の詳細推定:通勤ラッシュのピーク7-9時に集中。1時間あたり80人×2時間=160人、その他の時間20人×2時間=40人、計200人。客層は会社員70%(客単価500円:コーヒー150円+サンドイッチ350円)、学生30%(客単価300円:飲料+パン)。売上計算:200人×加重平均客単価440円=8.8万円。
昼の時間帯(10-15時):ランチピークの12-13時に60人、その他1時間20人×4時間=80人、計140人。オフィスワーカー80%(客単価750円:弁当500円+飲料150円+デザート100円)、その他20%(客単価500円)。売上:140人×700円=9.8万円。夕方(15-20時):帰宅ラッシュで1時間40人×5時間=200人。客単価600円(夕食材料、惣菜、飲料)。売上:200人×600円=12万円。
夜間(20-24時):1時間25人×4時間=100人。客層は近隣住民60%(客単価800円:酒類+つまみ)、残業帰り40%(客単価600円)。売上:100人×720円=7.2万円。深夜早朝(0-6時):1時間5人×6時間=30人、客単価500円。売上:1.5万円。
1日合計:8.8+9.8+12+7.2+1.5=39.3万円。駅前立地プレミアム1.3倍を考慮し、最終推定値は約51万円となります。
ファミリーレストランの月間売上
「ファミリーレストランの月間売上」を推定する場合は、席数×回転率×客単価×営業日数で計算します。郊外型店舗、席数80席、営業時間11-23時(12時間)と仮定。
平日の回転率:ランチ1.5回転(60席稼働)、ディナー1.0回転(40席稼働)、合計130人。休日:ランチ2.0回転(80席フル稼働)、ディナー1.5回転(80席フル稼働)、合計280人。客単価はランチ1000円、ディナー1800円の加重平均で1400円。
月間売上の計算:平日22日×130人×1400円=400万円、休日8日×280人×1400円=314万円、月間合計約714万円。ただし、天候や季節変動(夏休み・年末年始は1.2倍、2-3月は0.8倍)を考慮する必要があります。
また、テイクアウト売上が全体の15%程度あると仮定すると、714万円×1.15=約820万円が最終的な月間売上推定値となります。
都心の書店の年間売上
「都心の書店の年間売上」では、売場面積500㎡の中規模店舗を想定。1㎡あたりの月間売上を15万円(業界平均)とすると、500㎡×15万円×12ヶ月=9億円。
ただし、立地による補正(ターミナル駅隣接なら1.3倍)、品揃えの特徴(専門書中心なら客単価上昇、雑誌中心なら回転率上昇)、付帯サービス(カフェ併設なら売上10%増)などの要因を加味。最終的に9億円×1.3×1.1=約12.9億円と推定。
このように、基本の計算式に現実的な補正を加えることで、より説得力のある推定が可能になります。
まとめ:フェルミ推定を通じて得られる本当の価値
面接突破という短期目標の達成
フェルミ推定対策の第一の目的は、もちろん面接突破です。本記事で解説した4ステップの解法プロセス、基礎知識の暗記、頻出パターンの練習を実践すれば、面接本番で慌てることなく対応できます。
最後の1週間は、時間を計って実際の問題を解き、15分で一通りの回答ができるよう訓練しましょう。準備さえしっかりすれば、フェルミ推定は決して恐れる必要のない選考手法です。
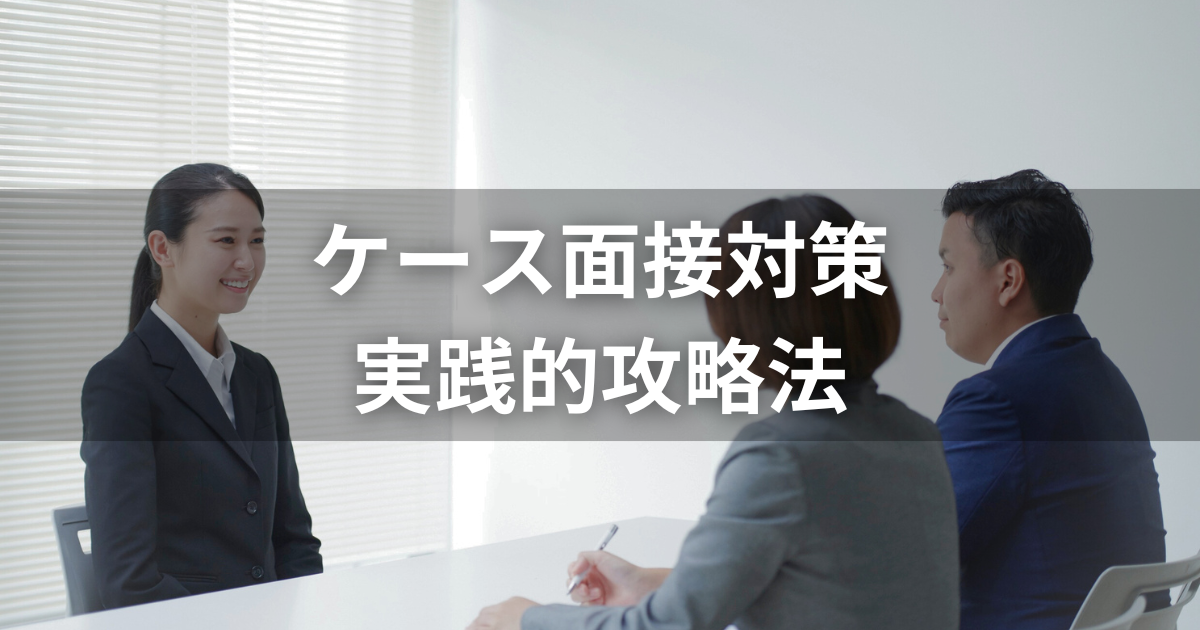

論理的思考力という長期資産の獲得
フェルミ推定で培われる論理的思考力は、キャリア全体で活きる貴重な資産となります。複雑な問題を構造化し、仮説を立てて検証するスキルは、プロジェクト管理、戦略立案、問題解決など、あらゆるビジネスシーンで応用可能です。
他のビジネススキルとの相乗効果も高く、データ分析やプレゼンテーション能力と組み合わせることで、より高い成果を生み出すことができます。
「くだらない」を「面白い」に変える視点
フェルミ推定を単なる選考対策と捉えるのではなく、知的なパズルとして楽しむ視点を持てば、学習はより充実したものになります。日常生活でも「このカフェの1日の売上は?」「この電車の乗客数は?」と推定してみることで、観察力と推論力が自然に鍛えられます。
思考ゲームとしての奥深さを理解すれば、「くだらない」という先入観は「面白い」という好奇心に変わるはずです。