コンサルフレームワーク一覧と使い方|実務で活かす方法

「実務で使えるフレームワークの一覧が知りたい」「3CやSWOTの具体的な使い方を学びたい」と考えることはありませんか。また同時に、「種類が多すぎて何を学べばいいか分からない」「知識として知ってはいるが、実務でうまく使いこなせない」といった悩みや、「型に当てはめるだけの思考停止に陥りたくない」という不安も抱えているのではないでしょうか。
この記事では、コンサルタントが実務で多用する必須のフレームワークを「戦略立案」「問題解決」など目的別に厳選して紹介します。さらに、多くの方が陥りやすい「落とし穴」と、それらを組み合わせて活用する「実践的な使い方」までを徹底的に解説します。
コンサルティングフレームワークの基礎理解
フレームワークとは何か-思考の型を身につける意味
フレームワークとは、単なるテンプレートや図表のことではありません。トップファームのコンサルタントたちが、複雑な問題を構造的に整理し、解決策を導くために磨き上げた「思考の型」そのものです。
例えばマッキンゼーやBCGといった企業は、長年の実践を通じてこれらの手法を体系化してきました。この「型」を身につけることは、戦略の立案や意思決定の質とスピードを飛躍的に向上させる第一歩となります。


なぜコンサルタントはフレームワークを使うのか
プロのコンサルタントがなぜフレームワークを多用するのでしょうか。その最大の目的は、限られた時間の中で最大の成果を出し、思考の「漏れ」や「ダブり」を防ぐためです。
コンサルティングの現場では、MECEの原則が徹底されます。フレームワークは、このMECEを担保しながら、問題を構造的に整理し、仮説を立てて検証する「仮説思考」を実践するための土台として機能します。情報を体系的に整理し、本質的な課題を特定するために必要不可欠なツールとして活用されているのです。
参考:MECE(ミーシー)とは?フレームワークや具体例をわかりやすく解説 – Salesforceブログ、仮説とは: コンサルの定番思考法で仕事のスピードアップを | GLOBIS学び放題×知見録

フレームワーク活用時の3つの落とし穴とその回避法
フレームワークの活用には注意すべき「落とし穴」があります。第一に、目的を忘れ、フレームワークに当てはめること自体が目的化してしまう「思考停止」です。第二に、ビジネスの具体的な文脈を無視し、機械的に適用してしまうこと。第三に、分析して満足し、戦略や行動に繋げられない「アウトプット偏重」です。
これらを回避するには、常に「なぜこの分析が必要なのか」という目的意識を持ち、フレームワークを万能の答えではなく、思考を深めるための視点を提供するツールとして使いこなす意識が重要です。
戦略立案のフレームワーク
3C分析-市場環境を立体的に把握する
3C分析は、戦略 立案の基本となるフレームワークです。市場・顧客(Customer)、自社(Company)、競合(Competitor)という3つの「C」の視点から、企業が置かれた市場環境を立体的に把握します。
さらに、顧客ニーズの変化を捉え、競合他社の強み・弱みと比較し、自社の成功要因(KSF)を見極めることが目的です。近年は、この3C分析をカスタマージャーニーマップと組み合わせ、顧客の行動変容に合わせた具体的なマーケティング施策を導き出すなど、デジタル時代の活用法が主流となっています。

SWOT分析-内部・外部環境から戦略オプションを導く
SWOT分析は、企業の内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を導き出す代表的なフレームワークです。内部要因である強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)、外部要因である機会(Opportunities)と脅威(Threats)の4象限に分けて要因を洗い出します。しかし、単に整理するだけでは不十分です。
重要なのは、これらを掛け合わせる「クロスSWOT分析」です。「強み」×「機会」で積極的な事業展開を、「弱み」×「脅威」で撤退や防衛策を検討するなど、具体的な戦略オプションを立案するために活用します。
参考:SWOT分析とは?やり方・戦略立案の方法をフレームワークで解説 | Salesforce
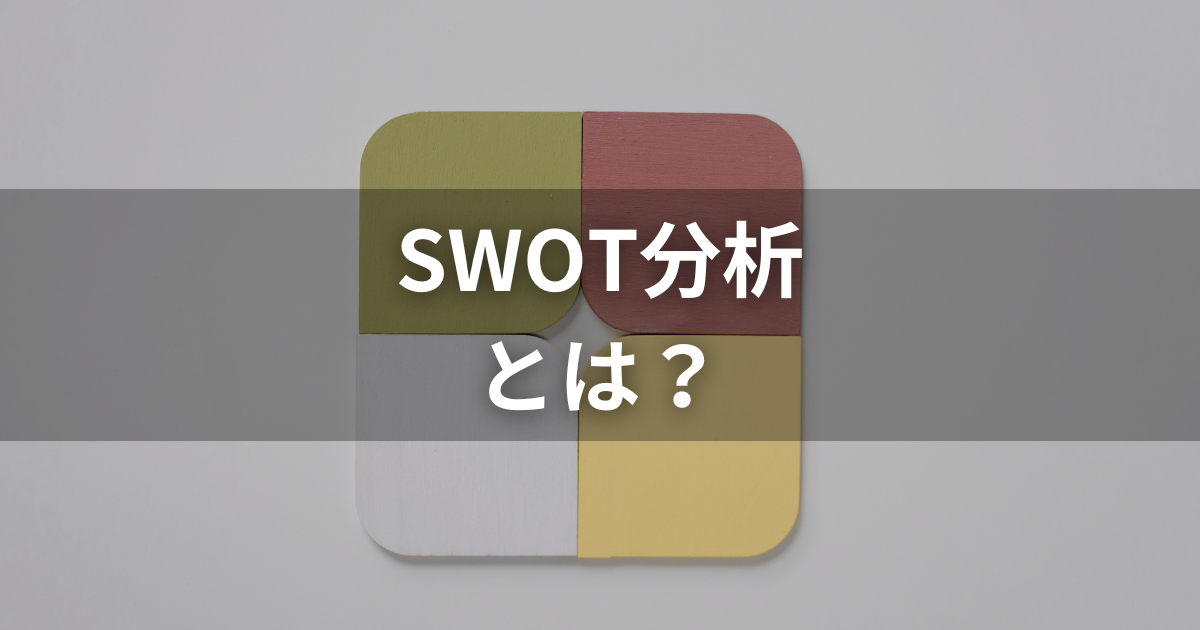
PEST分析-マクロ環境変化を先読みする
PEST分析は、企業活動に影響を与えるマクロな外部環境の変化を先読みするためのフレームワークです。政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの視点で、自社ではコントロールできない大きな流れを分析します。
例えば、法規制の変更(政治)や消費者の価値観の変化(社会)、新技術の登場(技術)などが、事業にとって「機会」となるか「脅威」となるかを検討します。近年はこれに環境(Environmental)や法律(Legal)を加え、PESTEL分析として活用する企業も増えています。
参考:PEST分析とは?目的、やり方・手順、注意点を解説 | コラム | 東大IPC−東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
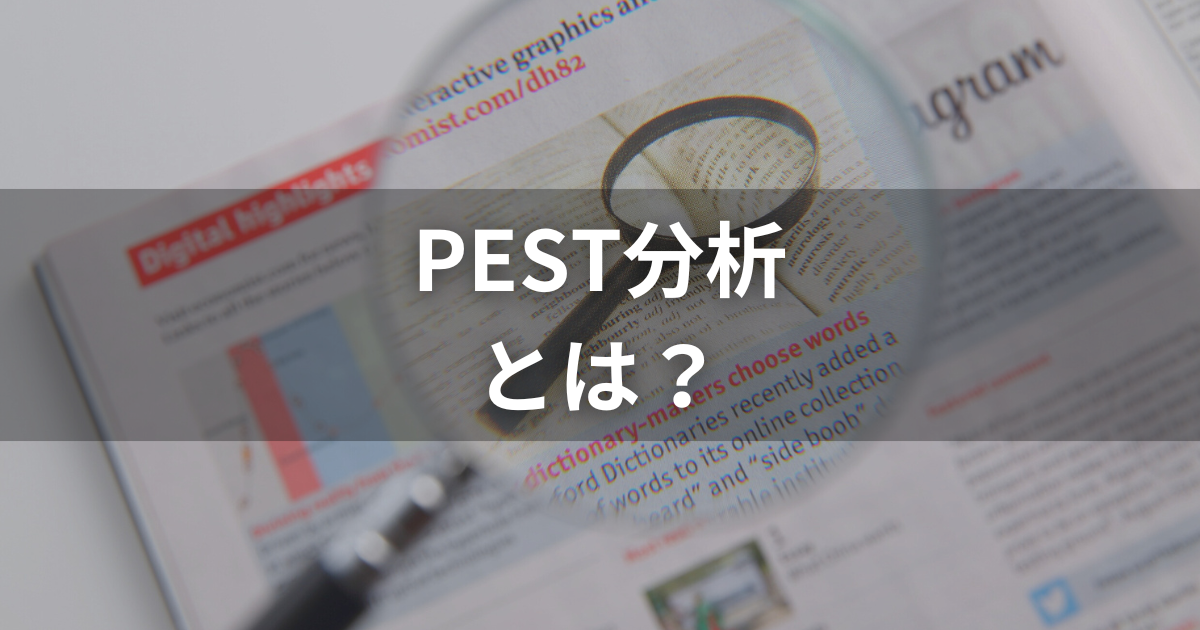
STP分析-ターゲット戦略を精緻化する
STP分析は、マーケティング 戦略を立案する上で中核となるフレームワークです。まず市場全体をニーズや属性で細分化し(Segmentation)、次にその中で自社が狙うべきターゲット市場を決定し(Targeting)、最後にターゲット顧客の頭の中で競合とどう差別化するか(Positioning)を定めます。
このフレームワークを活用することで、「誰に、どのような価値を、どのように提供するか」というマーケティングの基本戦略が明確になります。デジタルマーケティングにおいては、顧客データを活用してセグメンテーションをより精緻化し、個々の顧客に最適化されたアプローチを行うために活用されます。
参考:STP分析とは?マーケティングで重要な理由、やり方、注意点を解説 | コラム | 東大IPC−東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
ファイブフォース分析-業界構造から収益性を読み解く
ファイブフォース分析は、業界の構造と競争要因を分析し、その業界の収益性(魅力度)を評価するフレームワークです。マイケル・ポーターによって提唱され、①新規参入の脅威、②代替品の脅威、③供給者(売り手)の交渉力、④買い手の交渉力、⑤既存の競合他社との敵対関係、という5つの力(フォース)から分析します。
自社が属する業界の構造を理解し、これらの力に対してどのような戦略を採るべきか、あるいは魅力的な市場へ参入すべきかを検討するために活用される、企業 戦略の重要な分析手法です。
参考:ポーターの5フォース | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI)
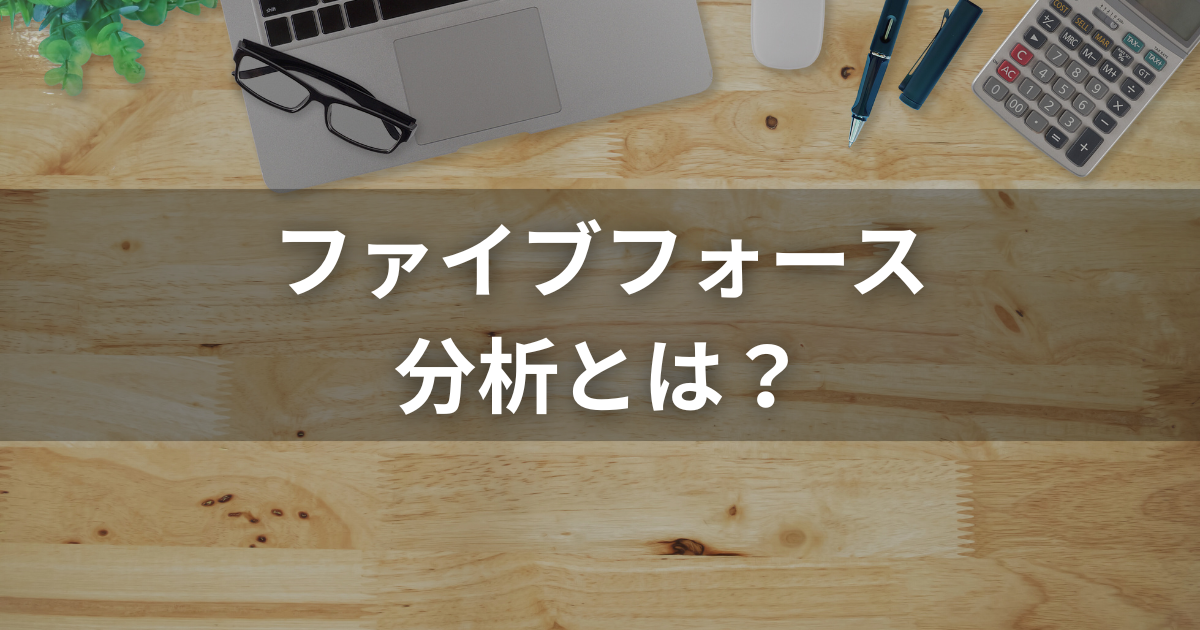
問題解決・改善策立案のフレームワーク
ロジックツリー-問題を構造的に分解する
ロジックツリーは、コンサルタントが問題解決を行う上で最も基本とするフレームワークの一つです。複雑で大きな問題を、MECE(漏れなくダブりなく)の原則に従って小さな要素に分解し、構造的に整理する手法です。
問題の原因を深掘りする「Whyツリー」、解決策を具体化する「Howツリー」、全体像を把握する「Whatツリー」などの型があります。これにより、問題の根本原因を特定しやすくなったり、具体的なアクションプランに落とし込みやすくなります。思考を可視化し、チーム全体で問題認識を共有するためにも極めて有効なツールです。

イシューツリー-本質的な論点を見極める
イシューツリーは、ロジックツリーと似ていますが、特に「解くべき本質的な課題(イシュー)」を見極めるために使われる思考整理術です。プロジェクトの初期段階で、「問題は何か?」という大きな問いを、「Yes/Noで答えられるサブイシュー」にまで分解していきます。
これにより、分析すべき論点が明確になり、無駄な作業を減らすことができます。例えば「売上を伸ばすべきか?」というイシューを、「市場は成長しているか?」「自社のシェアは拡大可能か?」といった具体的な論点に分解します。限られたリソースで成果を出すための戦略的な問題設定に役立ちます。
パレート分析(80:20の法則)-重要課題に集中する
パレート分析は、「ビジネスにおける成果の80%は、全体の20%の要因によって生み出されている」という「80:20の法則」に基づき、最もインパクトの大きい問題や課題を特定するフレームワークです。
例えば、「売上の80%は、全顧客の20%が生み出している」や「クレームの80%は、全製品の20%に集中している」といった傾向をデータから見つけ出します。この分析により、リソースをどこに集中すべきかが明確になり、効率的な問題解決や改善活動が必要となります。ABC分析と併用し、課題の優先順位を決定するためにも活用されます。
参考:パレートの法則 | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI)
PDCA×OODAループ-変化に強い改善サイクル
PDCA(計画・実行・評価・改善)は、業務改善の基本的なフレームワークとして多くの企業で導入されています。しかし、計画を重視するあまり、変化の速いビジネス環境では対応が遅れるという弱みも指摘されます。
そこで注目されるのが、OODAループ(観察・状況判断・決定・実行)です。OODAは、現場の状況変化を迅速に捉え、即座に判断・行動することを重視します。環境変化が激しい場合はOODAを、既存プロセスの着実な改善にはPDCAを、というように、状況や目的に応じて両者を使い分けたり、ハイブリッドで活用したりすることが、現代の企業には求められます。
参考:変化に強い「OODAループ」とは?「PDCAサイクル」との違い|ものづくりの現場トピックス | キーエンス
バリューチェーン分析-価値創造プロセスを最適化する
バリューチェーン(価値の連鎖)分析は、企業の事業活動を「価値」が創造される一連のプロセスとして捉えるフレームワークです。事業を「主活動(購買、製造、出荷、販売、サービスなど)」と「支援活動(人事、技術開発など)」に分解し、各活動がどの程度、最終的な価値(利益)に貢献しているかを分析します。
この分析を通じて、自社の強みや弱みがどのプロセスにあるのか、コストが過剰にかかっている部門はどこか、競合優位性を生み出す源泉は何かを特定します。事業全体の最適化と戦略立案に役立つ手法です。
参考:バリューチェーンとは?概要や分析方法、メリット、事例などを解説 Business Navi~ビジネスに役立つ情報~:三井住友銀行
組織・人材マネジメントのフレームワーク
7S分析-組織変革の全体像を設計する
マッキンゼーが開発した7S分析は、企業の組織文化や体質を多角的に把握するためのフレームワークです。組織を7つの「S」で始まる経営要素(戦略、組織構造、システム、共通の価値観、経営スタイル、人材、スキル)に分けて分析します。
これらは相互に関連しており、優れた戦略も、それを実行する組織体制や人材、価値観が伴わなければ機能しません。特に組織変革を行う際、ハードの3S(戦略、構造、システム)だけでなく、ソフトの4S(価値観、スタイル、人材、スキル)の全体的な整合性を取るために活用されます。
参考:マッキンゼーの7Sとは – 組織の「本当の実力」を丸裸にする診断ツール | GLOBIS学び放題×知見録
Will-Skill Matrix-人材配置を最適化する
Will-Skill Matrix(ウィル・スキル・マトリクス)は、人材育成や組織内での配置を検討する際に活用されるシンプルなフレームワークです。縦軸に「意欲(Will)」、横軸に「能力(Skill)」を取り、人材を4つの象限(例:高意欲・高スキル、高意欲・低スキルなど)に分類します。
このマトリクスによって、各社員が現在どの位置におり、企業としてどのような育成戦略を採るべきかが明確になります。タレントマネジメントシステムと連携させ、組織全体の人材ポートフォリオを可視化し、戦略的な人員配置を決定する上で役立ちます。
コンピテンシーモデル-成果を生む行動特性を定義する
コンピテンシーモデルは、企業や特定の職務において高い業績を上げる人材(ハイパフォーマー)に共通する「行動特性」を定義し、体系化したものです。これは、単なる知識やスキルではなく、「成果に結びつく思考様式や行動パターン」に着目する点が特徴です。
例えば、コンサルタントであれば「仮説構築力」や「顧客志向」などが該当します。このモデルを定義することで、採用時の評価基準、組織内での育成戦略、公正な人事評価の軸として一貫して活用できます。ジョブ型雇用が進む中で、職務に求められる具体的な行動を定義する上でも重要です。
デジタル時代の新フレームワーク
ビジネスモデルキャンバス-事業全体を1枚で可視化する
ビジネスモデルキャンバス(BMC)は、新しい事業の立案や既存事業の分析に用いられるフレームワークです。事業の全体像を「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「顧客との関係」「収益の流れ」「主要リソース」「主要活動」「主要パートナー」「コスト構造」という9つの要素に分解し、1枚のシートに可視化します。
これにより、ビジネスモデルの全体像と各要素の関連性が一目で把握できます。サブスクリプションやプラットフォームビジネスなど、複雑な収益構造を持つ現代の事業モデルを整理し、戦略を検討する上で非常に有効です。
参考:ビジネスモデルキャンバス|グロービス経営大学院 創造と変革のMBA
カスタマージャーニーマップ-顧客体験を設計する
カスタマージャーニーマップは、顧客が製品やサービスを認知し、購入し、利用後に至るまでの一連の体験(ジャーニー)を時系列で可視化するフレームワークです。顧客の行動、思考、感情、そして企業との接点(タッチポイント)を洗い出します。
このマップを作成する最大の目的は、企業 視点ではなく顧客 視点で体験を整理し、どの段階で顧客が不満を感じているか(ペインポイント)、あるいは満足しているか(感動ポイント)を特定することです。これにより、顧客体験(CX)を向上させるための具体的な改善の機会を見つけ出し、オムニチャネル戦略などに活用します。
参考:【テンプレート付】カスタマージャーニーとは?作り方や活用事例を簡単に解説 | Salesforce
デザイン思考×アジャイル-イノベーションを加速する
デザイン思考は、デザイナーが用いる思考プロセスをビジネス上の問題解決に活用するフレームワークです。顧客への深い「共感」から始まり、問題を「定義」し、アイデアを「創造」し、「プロトタイプ(試作)」を作り、「テスト」する、という5つのステップを踏みます。
このプロセスは、顧客本人も気づいていない潜在的なニーズを発見し、革新的な解決策を生み出すのに適しています。さらに、このデザイン思考で得たアイデアを、アジャイル開発の手法を用いて迅速に形にし、改善を繰り返すことで、イノベーションの実現スピードを加速させることができます。
OKR(Objectives and Key Results)-目標管理を革新する
OKR(Objectives and Key Results)は、Googleなどのシリコンバレー企業が採用する目標管理のフレームワークです。「Objectives(目標)」には、組織が目指す挑戦的で定性的なゴールを設定します。一方、「Key Results(主要な成果指標)」には、その目標の達成度を測るための定量的な指標を複数設定します。
OKRは、企業 全体の大きな目標と、各部門、各個人の目標をリンクさせ、組織 全体のベクトルを合わせることに強みがあります。従来のKPIが既存業務の管理に重きを置くのに対し、OKRは高い目標への挑戦とイノベーションを促す目的で活用されます。
実践編:フレームワークの組み合わせ技
戦略立案の黄金プロセス-複数フレームワークの連携
フレームワークは単体で使うよりも、組み合わせて使うことで真価を発揮します。戦略立案の黄金プロセスとして、まずPEST分析でマクロな外部環境を把握し、次に3C分析で市場・顧客・競合のミクロな環境を分析します。そして、それらの情報をもとにSWOT分析で自社の強み・弱み、機会・脅威を整理します。最後に、STP分析で具体的なターゲット市場を決定し、戦略を絞り込みます。
このように、複数のフレームワークを活用して分析の視点を連携させることで、戦略の精度を飛躍的に高めることが可能になります。
業界別フレームワーク活用パターン
活用すべきフレームワークは、業界や目的によって異なります。例えば、製造業であれば、バリューチェーン分析を用いてコスト構造や強みを分析したり、パレート分析で品質改善の優先順位をつけたりすることが有効です。小売業であれば、STP分析やカスタマージャーニーマップで顧客セグメントごとの施策を検討することが多いでしょう。
IT業界では、ビジネスモデルキャンバスやアジャイル開発が頻繁に用いられます。金融業界では、PEST分析による規制動向の把握が不可欠です。自社の業界特性と解決したい課題に応じて、最適なフレームワークの組み合わせを選択することが重要です。
プロジェクトフェーズ別の使い分け
コンサルティングのプロジェクトは、一般的に「現状分析」「課題特定」「戦略 立案」「実行計画」といったフェーズで進み、各フェーズで活用すべきフレームワークは異なります。
例えば、「現状分析」では3C分析やPEST分析で環境を把握します。「課題特定」では、ロジックツリーやイシューツリーで問題を分解・整理し、根本原因を探ります。「戦略立案」ではSWOT分析やSTP分析で方向性を決定します。「実行計画」では、PDCAやOKRを用いて具体的なアクションプランと管理手法を設計します。フェーズの目的に合わせた使い分けが成果に直結します。
よくある質問
まとめ:フレームワークを超えた思考へ
フレームワークの限界と創造的思考
本記事で様々なフレームワークを紹介しましたが、これらは思考の「補助線」に過ぎません。フレームワークに依存しすぎると、かえって思考が型にはまり、現実を見誤る「思考停止」の罠に陥ります。フレームワークは過去の成功パターンを整理したものですが、未来のビジネス環境は常に変化します。
本当に必要なのは、フレームワークを活用しつつも、それを疑い、自社の状況に合わせてカスタマイズし、時には捨てる勇気を持つことです。最終的な意思決定は、フレームワークの分析結果を超えた、独自の視点と創造的な思考によって下されるべきです。
継続的な学習とアップデート
ビジネス環境の変化に伴い、活用すべきフレームワークも日々進化しています。かつては万能とされた手法が現代の市場では機能しなくなる一方、本記事で紹介したOKRやデザイン思考のように、デジタル時代に対応した新しいフレームワークが次々と生まれています。
コンサルタントやビジネスパーソンにとって、一度学んだ知識に安住せず、最新の経営理論や分析手法をキャッチアップし続ける姿勢は不可欠です。また企業は、こうした継続的な学習を支援する環境を整え、組織全体の思考力をアップデートし続ける必要があると考えられます。


